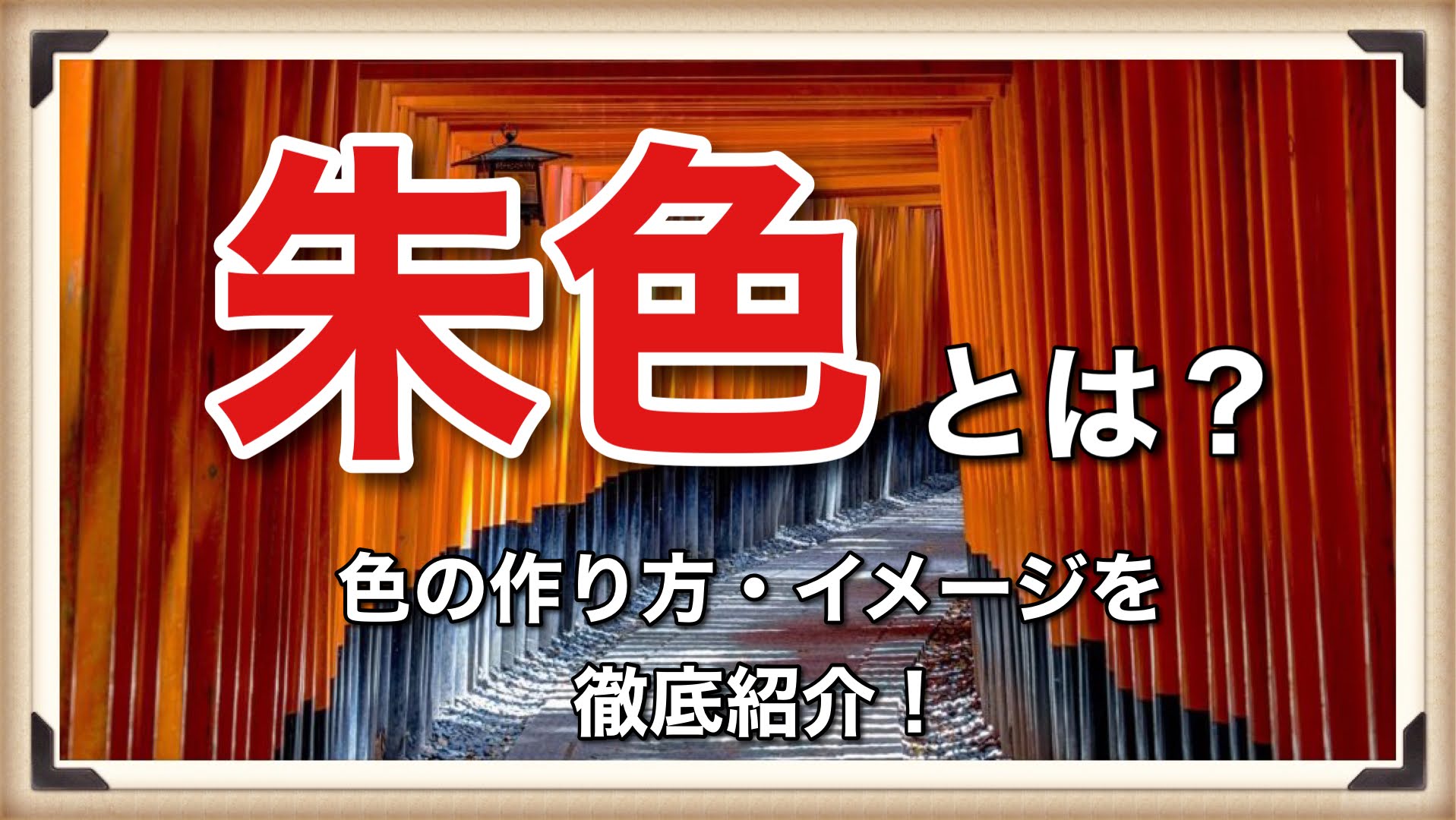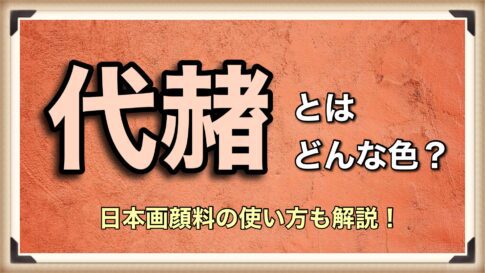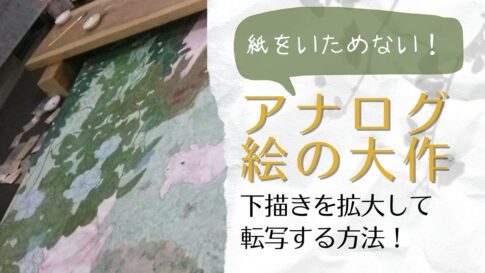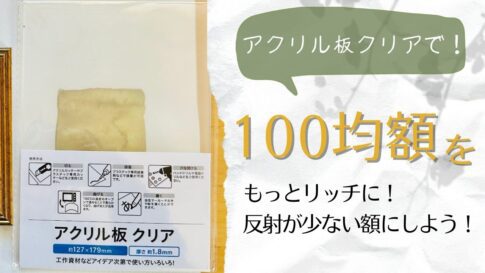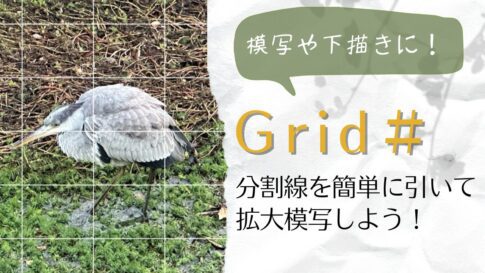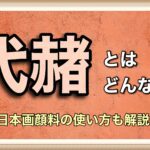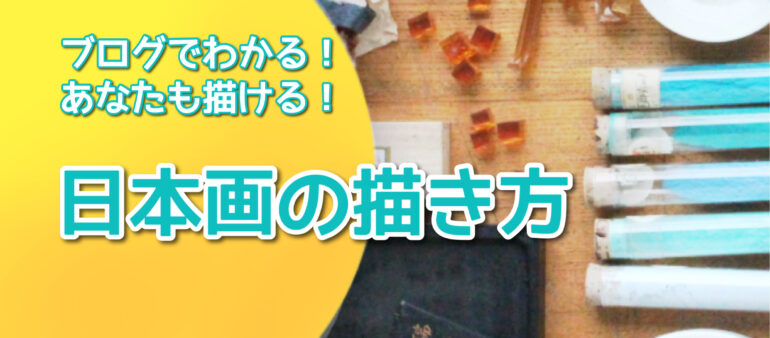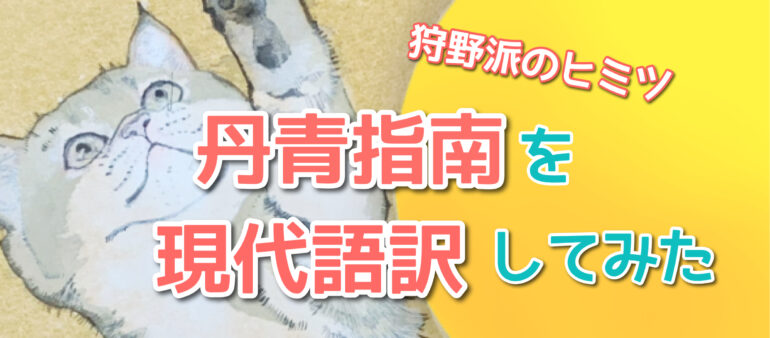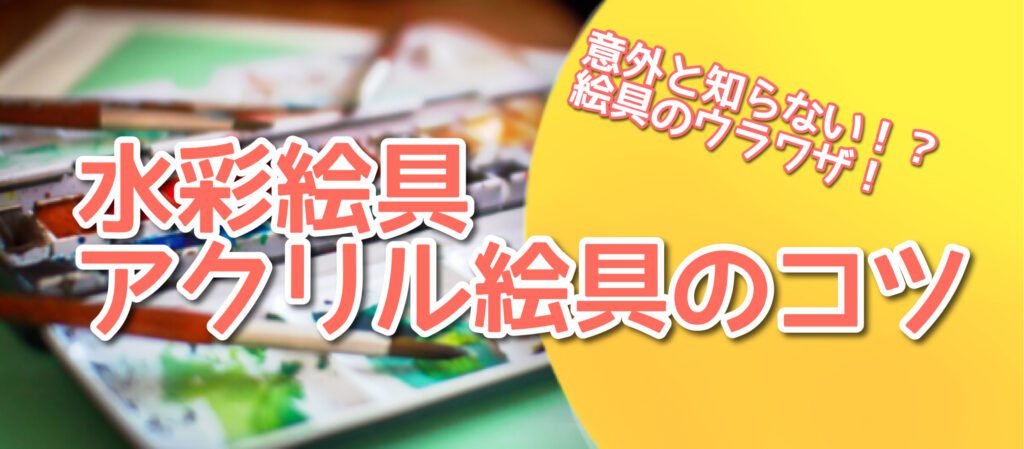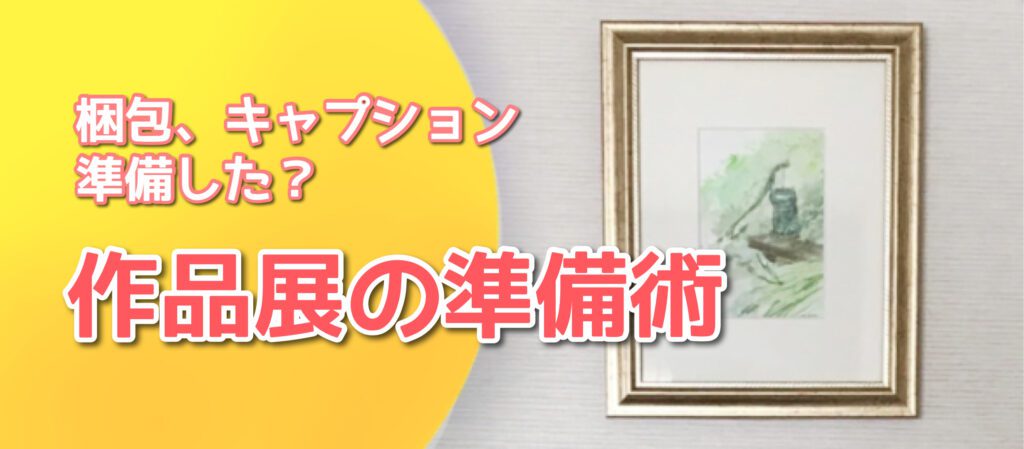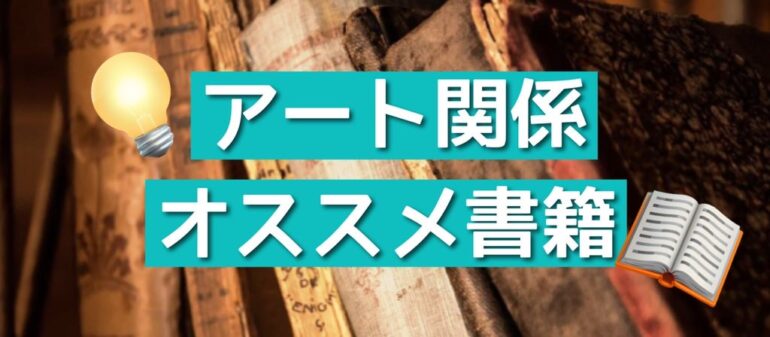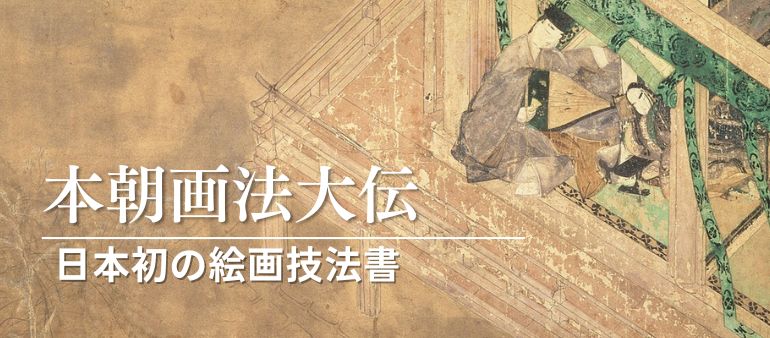- 朱色とは赤と黄色を混ぜた色!
- 朱色は高貴さと神聖さの象徴!
- 朱色の絵具の原料は水銀!
こんにちは、日本画家の深町聡美です。
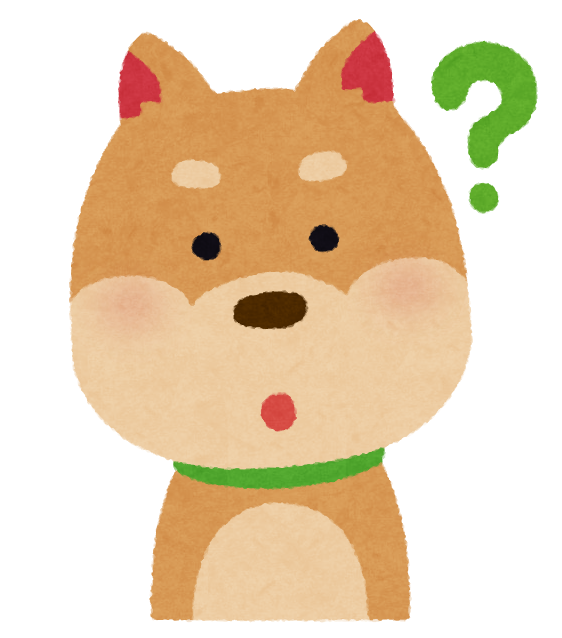
「しゅいろ」ってオレンジ?赤?
何でこんな色があるの?
朱色…
赤ともオレンジともつかない、
なんとも言えない色ですよね。
「お絵描きセットに入っているけど
使いどころがないな~」
と放置してしまっていませんか?
実は意外な成り立ちや、驚きの原料で
出来ている色なのです!
Contents
朱色とはどんな色?

| 三属性による表示記号 | 6.0R 5.5/13.5 |
| 慣用色名 | 朱色 |
| 絵具の原料 | 辰砂、硫化水銀 |
| 系統色名等 | 「わずかに黄みのさえた赤」 「黄みのさえた黄赤」 |
朱色は赤とオレンジの間の色です。
「わずかに黄みのさえた赤」
「黄みのさえた黄赤」とも表現されます。
朱色が使われる最も身近な場面といえば
神社の鳥居ですね。
豪華絢爛な赤っぽいオレンジ色に塗られている
のを見たことがあるでしょう。
それが朱色です。
また印鑑の朱肉、漆器にも朱色が使われています。
ヨーロッパでは「ヴァーミリオン」と呼ばれる赤が
近い色ですね。
朱色の絵の具の原料は?

AC写真
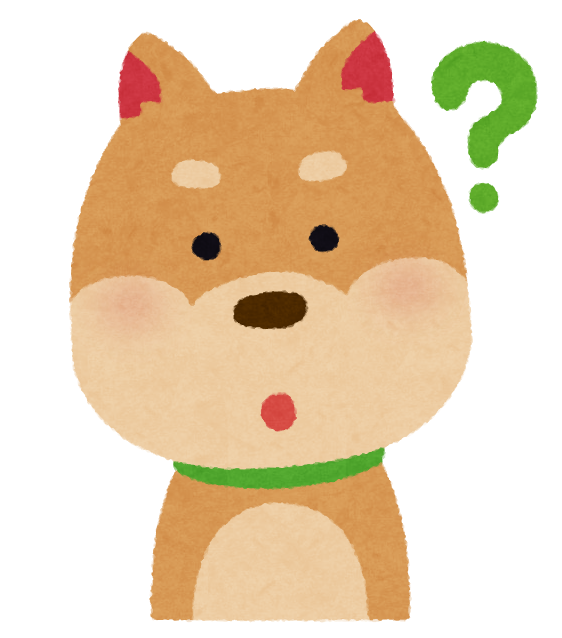
朱色ってどんな材料で出来ているの?
朱色の絵具の原料は硫化水銀です。
古代は朱砂、辰砂などの天然石を細かくして
絵具として用いていました。
辰砂はパワーストーンショップなどでも
扱われている天然鉱石なのですが、
毒性が強いことで規制の方向に向かっています。
そのため
「古代から使われた、本物の朱色」
は入手が難しくなってきているのです。
現在販売されている学生用絵具の朱色は
無害な別の物質で作られているので過度に
心配する必要はありませんよ。
ただ、日本画絵具やプロ用絵具の一部では
現在でも硫化水銀を素にした朱色があります。
(例:本朱)

天然辰砂以外の材料としては
9世紀に錬金術で発見された「銀朱」があります。
これは水銀と硫黄を人工的に合成して作った
硫化水銀となっています。
ところで、今ではどんな色も
「朱色=6.0R 5.5/13.5」
のように「決まった色」となっていますよね。
ですが、朱色の元々の原料は天然鉱物。
自然物なので、採取する地域によって色調は様々
でした。
他の岩石との比率や、温度によって
黄色っぽくなったり、黒っぽくなったり、
「100%決まった朱色」はなかったのです。
- 朱色の原料は硫化水銀(辰砂)
- 9世紀に発明された人工硫化水銀による朱色は「銀朱」と呼ばれる
- 天然石が原料なので決まった朱色ではなかった
朱色に似た臙脂色、茜色との違いは?

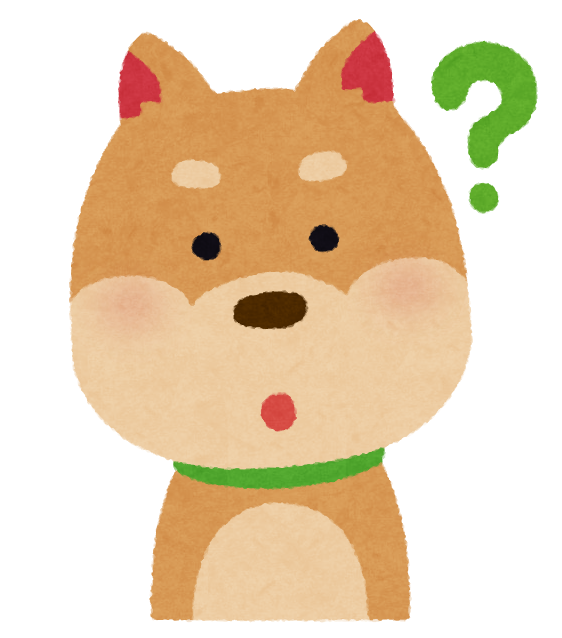
えんじ色やあかね色とはどう違うの?
水銀を使った絵具は怖いと思うかもしれませんが
他にも比較的安全な鉱物を原料にした赤い絵具も
あるんです。
それが「丹(に・たん)」。
こちらは酸化した鉛を用いた絵具です。
また、赤系の和色で良く聞くのは
「臙脂色(えんじいろ)」
「茜色(あかねいろ)」でしょう。
実はこちらは朱色や丹と異なり
染料が元になっている絵具です。
つまり壁画に塗るような塗料ではなく
染め物由来の赤色ということですね。
どれも日本の伝統的な赤色ですが
少しずつ由来や色が違うので覚えておくと
いいですよ。
- 朱色に似た日本の色には「丹(に・たん)」「臙脂色(えんじ)」「茜色(あかね)」がある。
西洋の色ではヴァーミリオンが近い
朱色の歴史

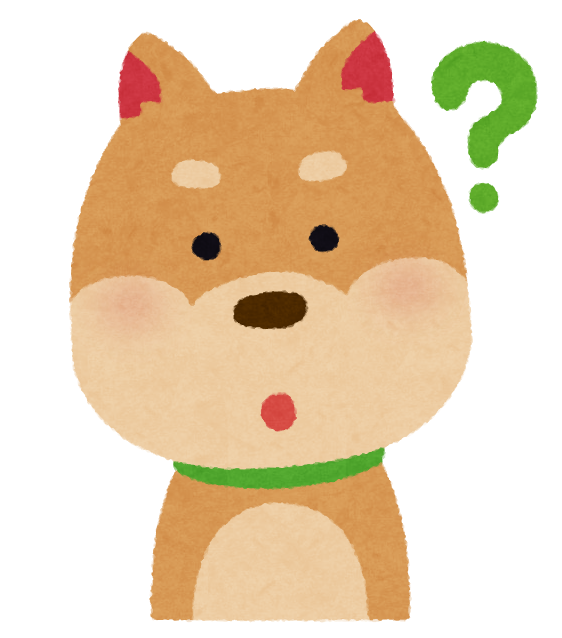
朱色の始まりや歴史ってどんな感じなんだろう?
朱色の始まりは中国だと言われています。
天然に産出する朱砂の中では
中国の辰州産の朱色が特に有名でした。
なので天然の朱色の絵具を「辰砂」と
呼ぶようになったのです。
そして古代中国、殷(紀元前17世紀~)
の時代から寺院や絵画の着色に
使われていたことが確認されています。
それだけ古くから中国では好んで使われて
いたんですね。
現在は「代表的な赤色」といえば、
日の丸のような赤色が思い浮かびますが、
昔の中国では朱色こそが「赤の中の赤色」
と考えられていました。
例えば陰陽五行思想に基づいた「四神」。
南を司る「朱雀」は朱という漢字が入っています。
これは朱色こそが赤色と考えられていた
ためだと言われています。
…
中国で始まり、そして重要視されてきた朱色。
朱色は日本にも大きな影響を与えました。

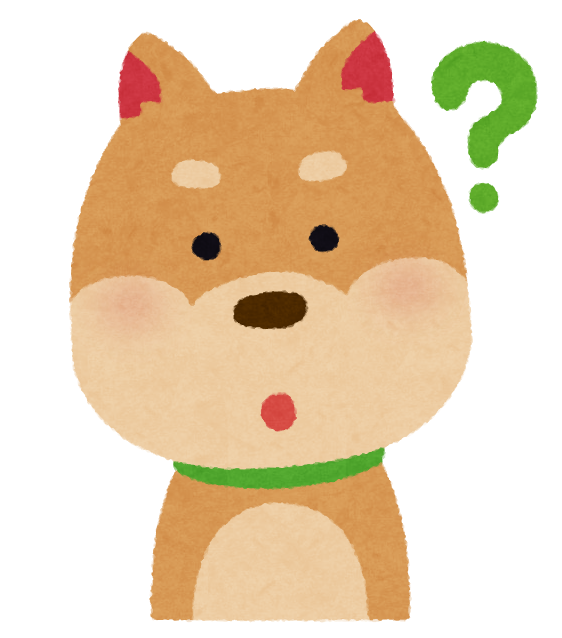
日本ではどのように活用されてきたの?
中国からやってきた朱色と、
その高貴なイメージは日本にも広がりました。
例えば宮城の正門である朱雀門は
朱色に塗られていたと言われていますし、
今でも馴染み深い神社の鳥居も
朱色ですよね。
このように日本でも朱色は尊い色として
用いられるようになりました。
また、日本でも古くから辰砂は採掘されており
手に入りやすい絵具だったと言えるでしょう。
他にも平安時代の傑作
「地獄草子」の炎も数種類の朱色が使われている等
様々な絵画で用いられていました。
そして、現在では馴染みが薄くなった朱色ですが、
明治の小学生向け色彩教育本では、
基本的の色の一つとして紹介されています。
(榧木寛則「小学色図解」(1876年))
さらに、1977年に20歳前後の女性を対象にした
調査では全体の17%が好きな色に
選んでいました。
朱色は、日本でも古くから非常に好まれた
色だったのです。
- 朱色の始まりは中国の辰州の砂
- 中国や日本で高貴な色として親しまれた
朱色のイメージと意味

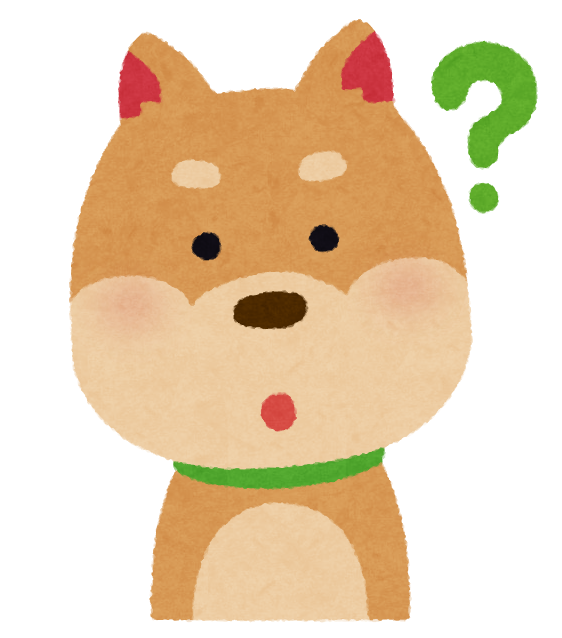
朱色にはどんなイメージや意味があるの?
朱色の主なイメージ・意味は
「権力、高貴、お守り、太陽」です。
古代中国では朱色は権力の象徴でした。
この頃は名家の家の門だけが、
朱色に塗ることを許されていました。
つまり地位の高い役職に就ける人
=朱色の門の家に住んでいたのです。
また、この高官たちは朱輪という
朱色の車にも乗っていました。
これらのことから、中国では
朱色は尊い色、権力を象徴する色として
苗字にもなっています。

日本でも朱雀門や神社の鳥居などに
権力やパワーの象徴として用いられて
いますよね。
「魏志倭人伝」では男子が朱で刺青をして
魔除けとしたと記述があります。
またサメ避けのお守りとして使われていました。
以上から朱色は赤色と同様に
火、太陽を想像させる、力を与える色だと
考えられていたことが分かります。
そして朱色の特に珍重された効力として
防腐剤の役割があげられます。
硫化水銀の辰砂は、火傷や皮膚の化膿に
効果があり、赤チン(消毒液)として
使われました。
また不眠やめまいにも用いられたと言います。
他にもエジプトでは防腐剤としてミイラに
塗られたり、日本でも古墳から身分が高い人物と
共に採掘されることがありました。
朱色は血液の連想と科学的な効能がリンクして
高貴さ、守護などのイメージが形作られていった
と言えるでしょう。
- 朱色は中国では権力の象徴として尊ばれた
- 朱色は赤と同じくパワーやエネルギーも象徴していた
アクリルガッシュでの朱色の作り方

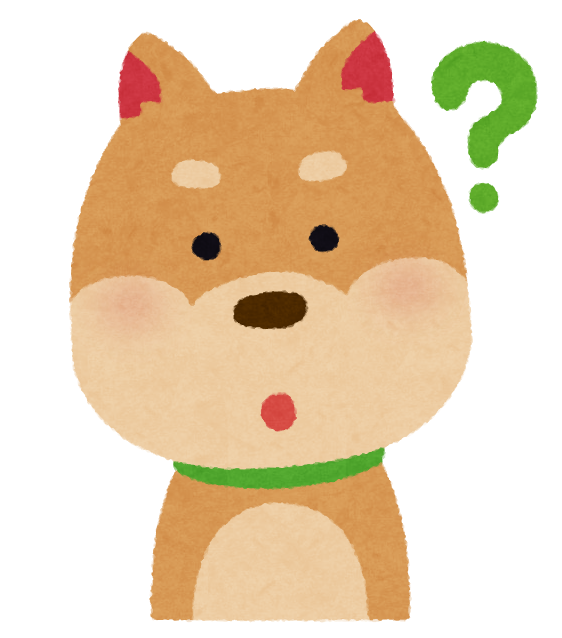
朱色のことは分かったけど、絵具ではどうやって作るの?
朱色は赤とオレンジの中間の色。
だから絵具で朱色を作る時は
赤とオレンジを混ぜるようにしましょう。
オレンジがない時は、黄色を少しだけ混ぜます。
今回はアクリルガッシュを使って
4種類の方法で朱色を作りました。
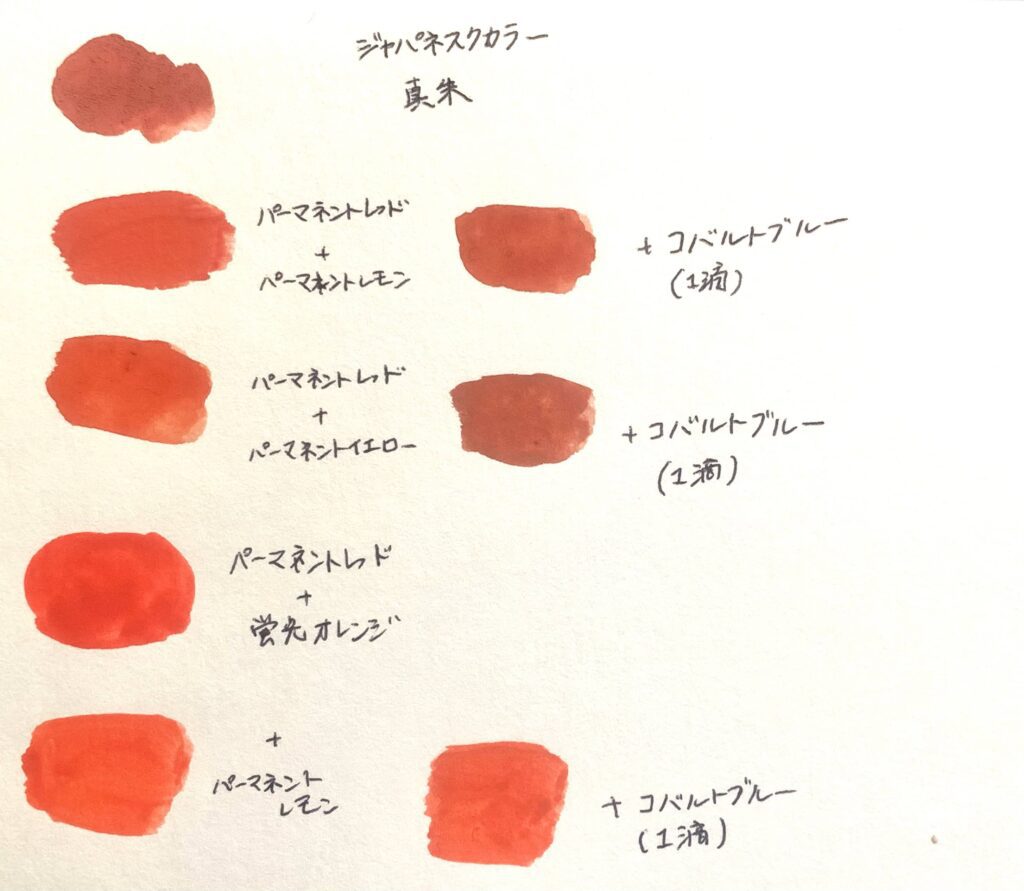
- ジャパネスクカラー真朱
- パーマネントレッド+パーマネントレモン
- パーマネントレッド+パーマネントイエロー
- パーマネントレッド+蛍光オレンジ
ジャパネスクカラー真朱はアクリルガッシュの
日本色シリーズです。
これ一本で真朱色となりますが、
鳥居の朱色より白っぽい、ピンク系の色です。
朱色特有の黄色っぽさは少ないですね。

©DARENIHO
②パーマネントレッド
+パーマネントレモン
こちらはおよそ
レッド:レモン
=2:1
で混色しています。
1:1ではただのオレンジになってしまう
ので、注意しましょうね。
レモンが白っぽいためか、
全体的にマットで明度が高く、
彩度は少し低めです。
コバルトブルーを一滴足すことで
少し深みのある色になりました。

©DARENIHO
③パーマネントレッド
+パーマネントイエロー
こちらが4種の中では
神社の朱色に最も近い色になりました。
こちらも2:1の割合で混ぜています。
しかし乾燥すると白くなってしまうので、
もう少し彩度を上げたい所です。
④パーマネントレッド+蛍光オレンジ
彩度を下げないために蛍光色を
混ぜてみました。
今度は1:1程度の割合です。
彩度は上がりましたが、朱色の
黄みが減ってしまいました。
パーマネントレモンを混ぜて
黄みを補ってあげると良いでしょう。
塗り重ねることではっきりした
朱色になるはずです。
- 絵具で朱色を作る時は、赤と黄色を混ぜよう!
赤を多めにするのがポイント!
日本画での朱色の作り方・使い方

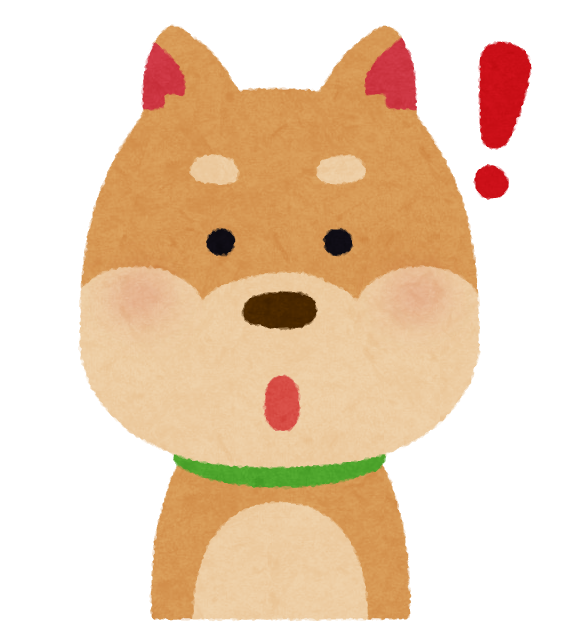
日本画の朱は、ほかの絵具とは使い方が違うんだって?
どうやって使うの?
さて、日本画における朱とは
赤色の顔料のことを指します。
日本画で朱という場合は硫化水銀から
作られた朱色の絵具を言うことが多いですね。
他の多くの天然岩絵具と同じく、
混合比や温度調節によって色味が変わり
黄口朱、赤口朱、鎌倉朱、鶏冠朱、黒朱
などがあります。
硫黄(硫化)成分ゆえに銀箔や銀泥を
黒変させてしまいますので、
併用するときは銀箔に硫化止めを
施しておきましょう。
その一方で、鉛系顔料を変色させるとも
言われていますが、
こちらは本当かどうか明らかではない
とのことです……
朱を作る手順①膠と混ぜる!
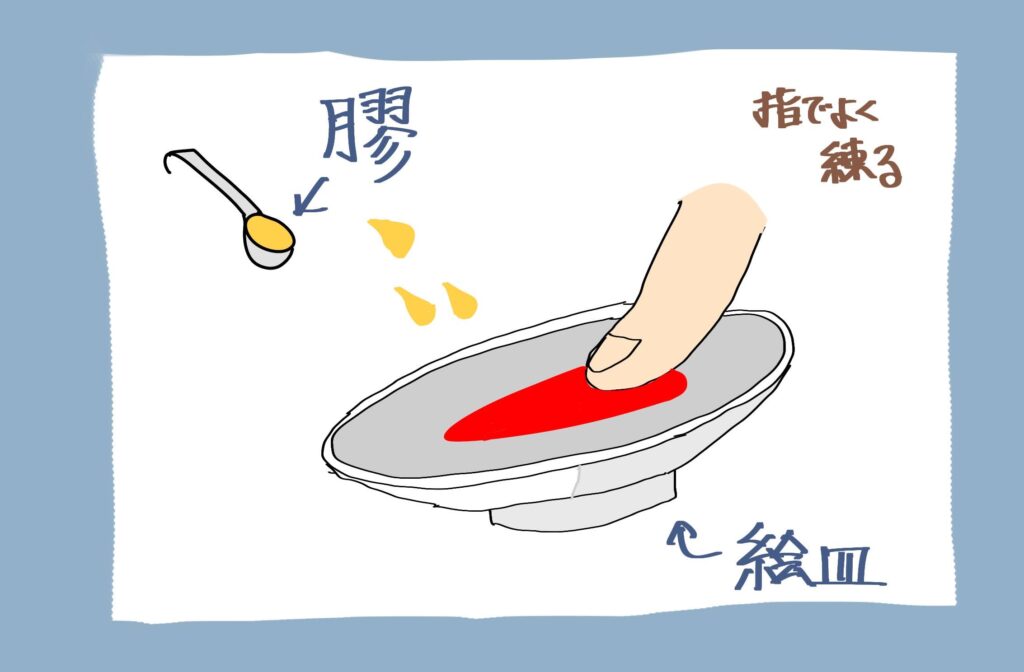
- 朱
- 膠
- 絵皿
- 水
以上の必要な物が揃ったら、
まずは朱を絵皿に出して膠を少量加えます。
そして、指でよく練りましょう。
朱を作る手順②水を加える
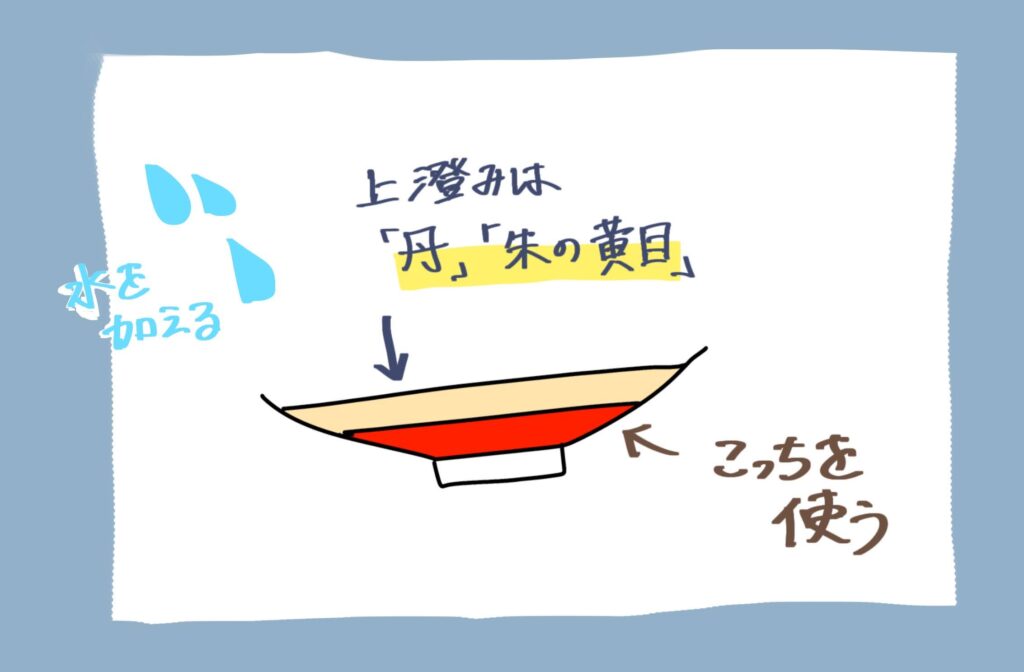
水を加えて指で良く練り溶かします。
その後しばらく放置して、
上澄み液と沈殿物に分離させましょう。
沈殿した物が朱となります。
※上澄みは「朱の黄目」「丹」になる。
朱を作る手順③朱の二度溶きをする
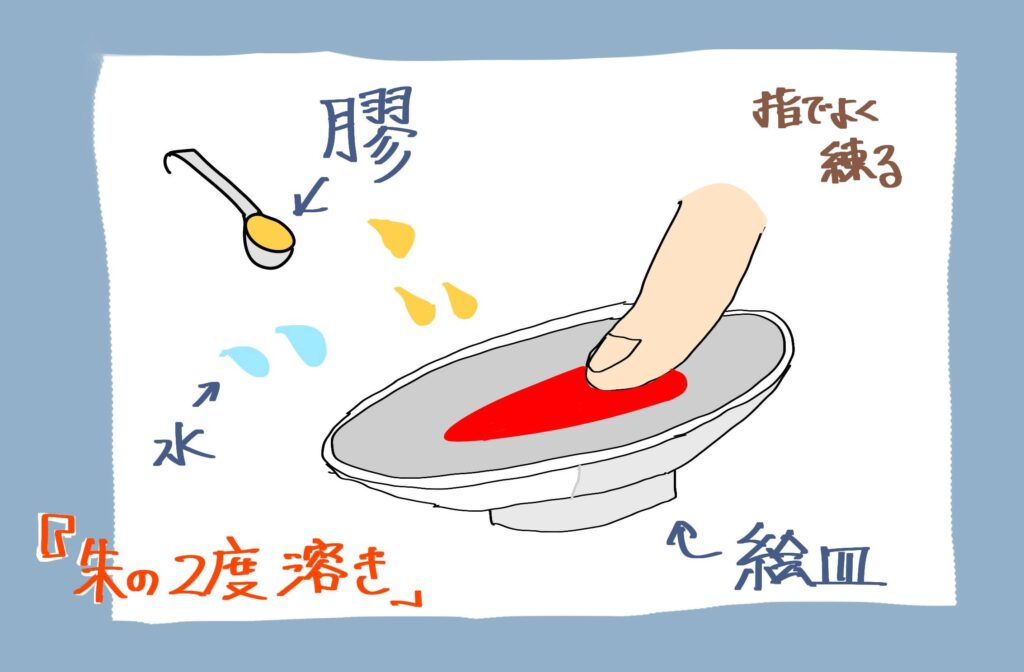
朱は非常に比重が重たい絵具。
(天然緑青3.7~4.0に対し8.2)
そのため膠が絵具粒に絡みづらく、
剥離の原因になることも…
なので、朱を解く場合は
「二度溶き」でしっかり膠分を付けることが
が推奨されています。
ということで、
沈殿した朱に膠を一滴加え、少量の水を加えて
指で練り溶きます。
これで朱の絵具の完成です!
はじめにアルコールで練ってから
膠を加えると混ざりやすくなる。
【必見】日本画における朱の注意点!

このように日本画では朱、つまり
硫化した水銀を手でこねこねして
溶かすわけです。
そして、硫化水銀は超、毒です。
そのため、
- 朱のついた手で顔を触る
- 口に入れる
- 水に流す
- 燃やす
ことは絶対にしないでください。
残った絵具は布でぬぐい、
燃えないゴミに出しましょう。
「るつぼの中に入れ
釉薬を以て密閉して焼けば」大丈夫!
という記述があっても、絶対に焼いては
いけません。
(「日本画 画材と技法の秘伝集」p59より)
- 口に入れること
- 火にかける、焼くこと
- 水に流すこと
上記のことは決してしないこと!
死にます。
まとめー【絵具】朱色とは?色の作り方と意味・イメージを徹底紹介!【日本画】

最後までお読み頂きありがとうございます。
以上が朱色の意味、イメージ、歴史、
そして絵具での作り方でした。
朱色は硫化水銀でできていて、
中国で採取された辰砂が主な原料でした。
日本に広がってからも、
高貴、権力、太陽などのイメージを持ち、
鳥居や工芸品、絵画に用いられて
きたんですね。
皆さんも歴史を感じながら、朱色の絵具を
使ってみて下さいね!
(日本画の「天然の朱」を使う時には
子供だけで作業しないようご注意下さいね!)
狩野派の朱色の使い方ー丹青指南現代語訳

この現代語訳は筆者が趣味で行いました。
大正時代の文章の専門家ではないので
間違い等あることを承知の上で
ご覧下さい。
↓原文はこちらでお読み頂けます。
国立国会図書館「丹青指南」
電子書籍&
ペーパーバック発売中!
原文が本で読めるようになりました!
一、朱
この絵具は水銀を蒸し焼きして作った物で、
使わない時に粉状に擦ったり、
溶いて置いたりするのは良くない。
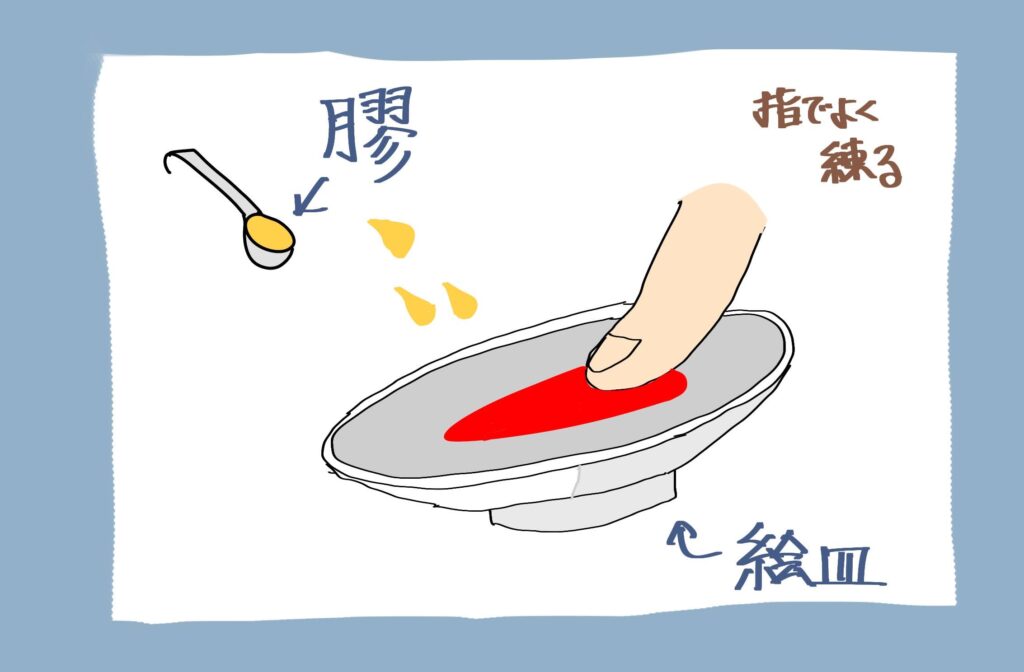
使う時に絵具皿に膠を溶かして
その中に入れて、指で練擦しながら
水で溶いて使うのが良い。
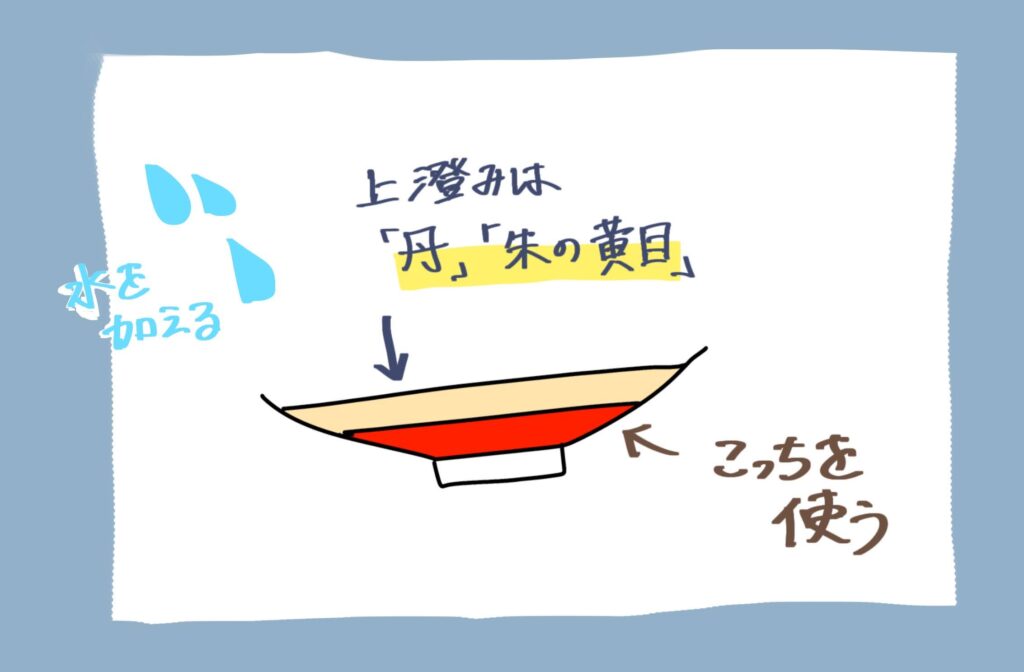
このようにして練った朱は
色が濃い部分は沈殿し、
黄色みを帯びた液が上澄みになる。
その上澄み液を「朱の黄目」と呼んで、
他の絵具皿に取り分けて所持し、
これを胡粉に混ぜて朱肉色として
人物一般の肌色に使う。
この練り朱が自然に乾いた時は、
再び練り直して使う。
といっても、これを度々すると
最終的に色相を損なうので捨てるようにする。
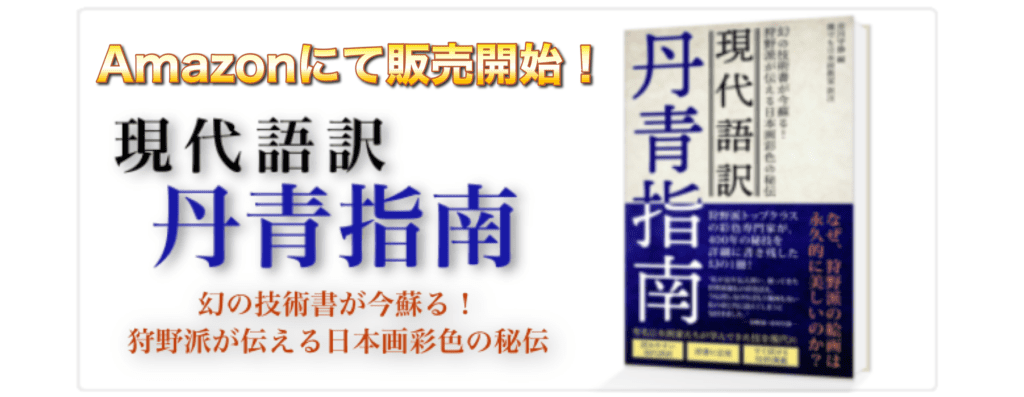
参考文献はこちら!
おすすめ!
日本画プレイヤー必読!
基礎から応用まで
すべての技法がわかる本!
東西の色の由来や
なりたち、色同士の文化的
関係性が分かる本!
かなりおすすめです!
色の由来が分かる辞書!
参考文献は「日本色彩事典」
ですが、現在購入しやすいのは
こちらの本です。
↓日本の色彩に関するお話↓
前の記事はこちら!
次の記事はこちら!