こんにちは、日本画家の深町聡美です。

今回は狩野派のハウツー本から、江戸時代の臙脂色の使い方を紹介します!
「昔の絵具~?
チューブに入ったのを輸入してたんじゃないの?」
実は違います!
特に臙脂色の絵具は、円盤状の綿でした!
一体そんな綿で絵は描けるのか!?
一体どうやって使っていたのか!?
昔の日本画の、臙脂色の使い方を解説します!
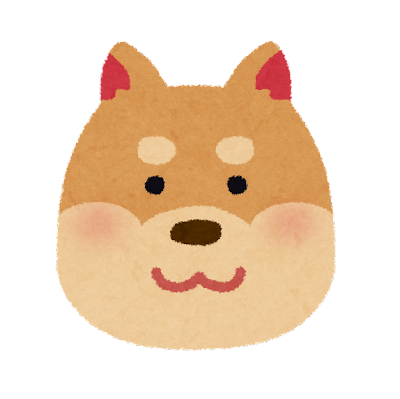
臙脂色ってどんな色だっけ~?
こちらの記事をご覧下さい!
Contents
臙脂色の絵具の原料は?

臙脂色の由来や材料は前の記事でお話した通り!
そして臙脂色の絵具は材料や作り方で、
三種類に分類されます!
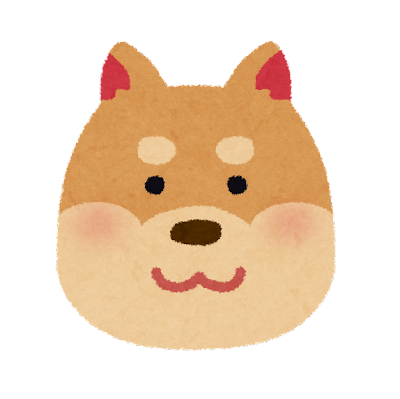
前記事を読んだ人もおさらいしよう!
1:ラックによる臙脂(生臙脂)

Sandeep HandaによるPixabayからの画像
インドやミャンマーなどに生息する
ラックカイガラムシの色素を、
円盤状の綿に浸したものです。
これを生臙脂(キエンジ)と言います!
奈良時代ごろから中国から輸入していましたが、
現在では作り方が失われた貴重な絵具です。
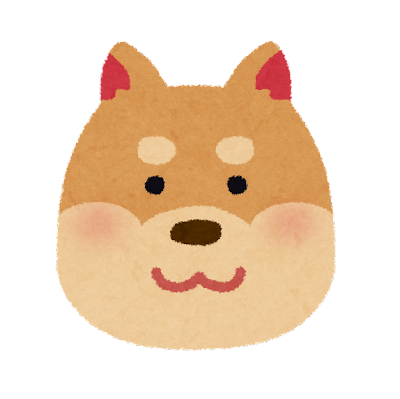
江蘇省揚州のものが上級品だったんだって
2:紅花による臙脂(正臙脂)

Julio César GarcíaによるPixabayからの画像
ふたつめは紅花から色素を抽出した
正臙脂(ショウエンジ)!
一見黄色い花ですが、
水に浸して黄色い色素を除去した後、
藁灰の灰汁で赤色の色素を抽出できます。
それに米酢や梅酢(烏梅)を入れると
赤く発色して一晩ほどで沈殿します。
これが顔料になるんですね!
この作り方の臙脂が、本来のものということで
正臙脂(ショウエンジ)なんです!

古代中国でも頬紅や口紅として使われていました!
3:蘇芳による臙脂(キエンジ)

江戸時代には蘇芳にミョウバンを入れて
赤くしたものも臙脂と考えられました。
狩野派の絵画本「丹青指南」では
蘇芳に胡粉を入れて絵具にしたものを
「キエンジ」として紹介しています。
この臙脂絵具の作り方は
貝原益軒の『大和本草』でも言及されています。
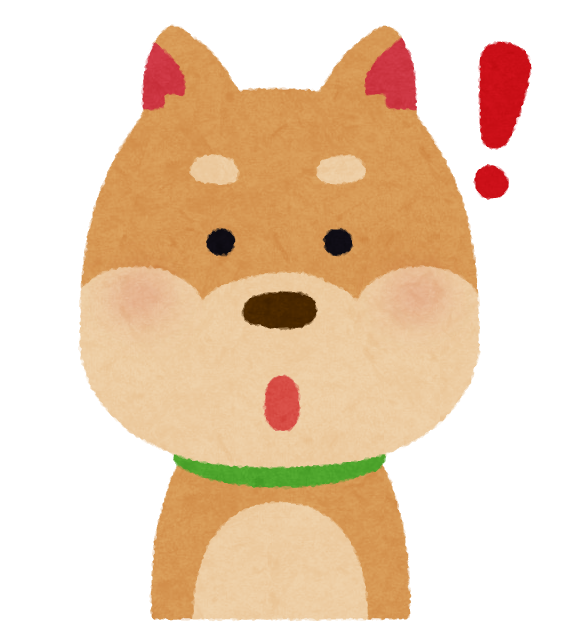
いろんな工夫をして赤い絵具を作っていたんだね!
江戸時代の臙脂絵具は綿だった!?

Martin HettoによるPixabayからの画像

昔の臙脂は、円盤状の赤い綿として輸入されました!
ラックによる臙脂で書いたように、
臙脂は他の日本画絵具のように粉ではありません。
江戸時代ごろの狩野派が使っていたのは
「中国の江蘇省揚州付近の紫草」を
平たい円形の綿に浸して乾燥させたものでした。
【日本画豆知識】奥村土牛も愛用した画材・綿臙脂(わたえんじ)。絵具として使うと、とても優しいピンク色に。実はカイガラムシの体液から作られていて、この色素は口紅などにも使われているんですよ。(山崎)@山種美術館 pic.twitter.com/ELgsFrSxH0
— 山種美術館 (@yamatanemuseum) March 17, 2016

ラック色素による臙脂が多いようです。
見た感じ通販で取り扱いがあるのは
丹青堂だけのようでした。
紅花?紫草?
じつは古代の臙脂絵具に使われた草は
はっきりしていないのです。
歴史が古い絵具なので、
紅花、オトギリソウ、紫草、蘇芳、ラック、
コチニールなどの様々な素材が使われたと
考えられています。
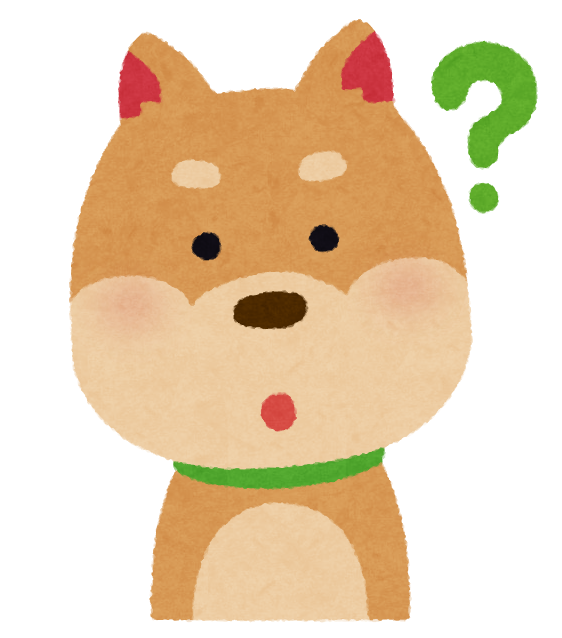
こんな綿の円盤なんて、どうやって使っていたの?

「丹青指南」という本から、この円盤臙脂の使い方を見ていきましょう!
江戸時代の臙脂色の使い方
天野山文化遺産研究所によるFB投稿
使い方はなかなか複雑です。
- 細かくちぎる
- お湯に浸けて紅汁を絞り出す
- 焼き付けを行う(乾燥させる)
「干上がらせるの!?」
という感じですよね。
ですが、
雑にやってしまうと発色が落ちてしまいます。
多少手間を掛けても
綺麗な色を目指したいですね!
①小さく切り取ろう!
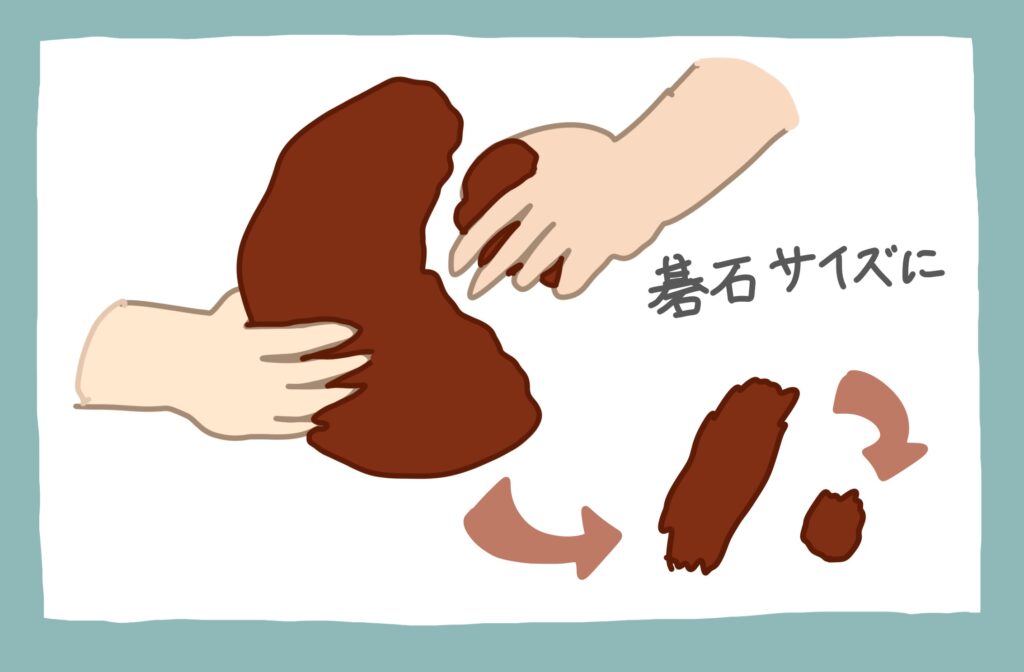
まずは小さくなるまで引きちぎります!
臙脂の円形が大約21〜24cmのものと仮定します。
その4分の1、もしくは3分の1ほどを切り取り、
さらに引き裂いて、碁石くらいの大きさにします。
②少なめの熱湯を入れる!
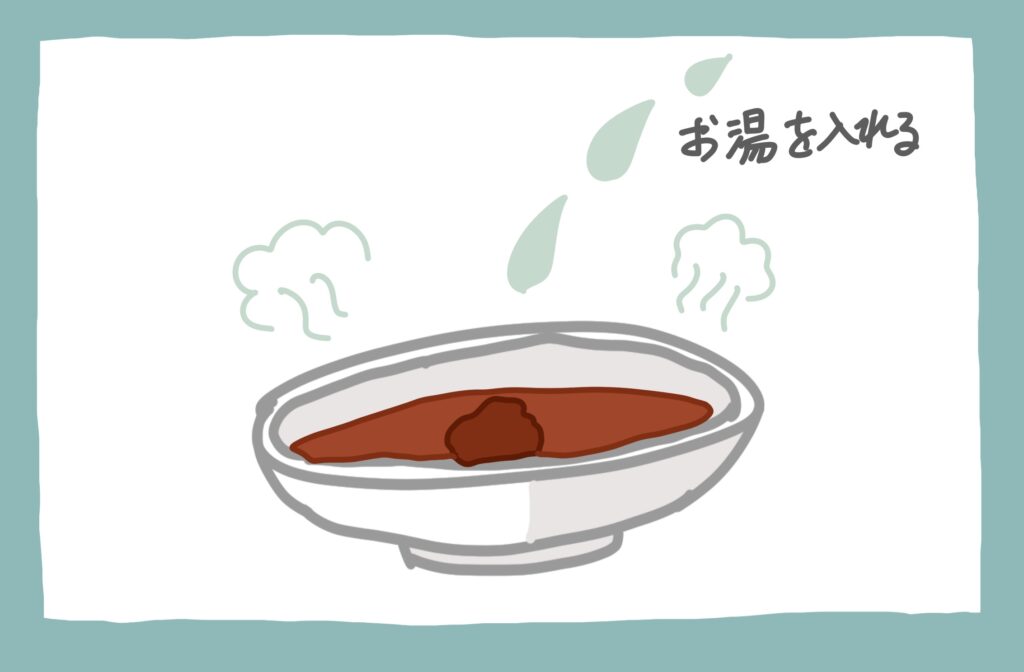
絵皿に入れて、熱湯を注ぎます。
お湯は少なめにしましょう。
乾燥させる(焼き付け)作業に
時間がかかってしまいます。
③綿を絞ろう!:第一番汁

紅綿をしぼりましょう!
すぐに紅色の汁になるので、
お湯から綿を取り出します。
綿に含んでいる紅汁を浸っていた絵皿にしぼります。
これを「第一番汁」といいます。
④綿を絞ろう!:第二番汁

別の絵皿に同じことをします!
しぼった綿をほかの絵皿に入れて、
また熱湯を注ぎます。
お湯が赤くなったら同じ絵皿にしぼります。
これを「第二番汁」とします。
⑤蓋をして一晩放置
二つの絵皿にラップをして一晩放置!
埃やゴミが入らないように
仮蓋(ラップ)をしておきましょう。
⑥一番汁と二番汁を混ぜる!
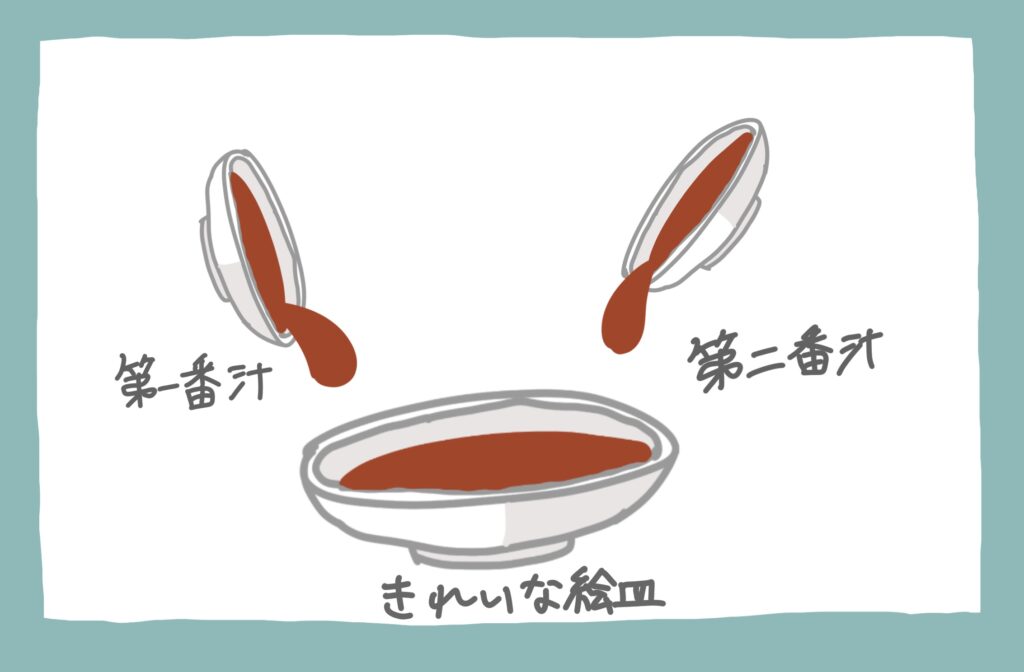
一番汁と二番汁を合わせます!
一晩置いておくと、紅汁はさらに澄んで、
鮮やかで明るくなります。
沈殿物が紅汁と混ざらないようにして
一番汁と二番汁を混ぜます!
混ぜた紅汁は他の絵皿に移しましょう。
⑦ゆっくり煮沸!

絵皿を湯煎します!
二つの紅汁を混ぜた絵皿を
お湯か水を入れた鍋に浸して煮沸します。
すると、水分が蒸発して赤い絵具が
絵皿にカピカピに乾きます。
その絵皿を絶えず動き揺らしながら、
臙脂を乾燥させていきます。
現代では
保温トレイ等を活用!
⑧完成!蓋をしておこう!
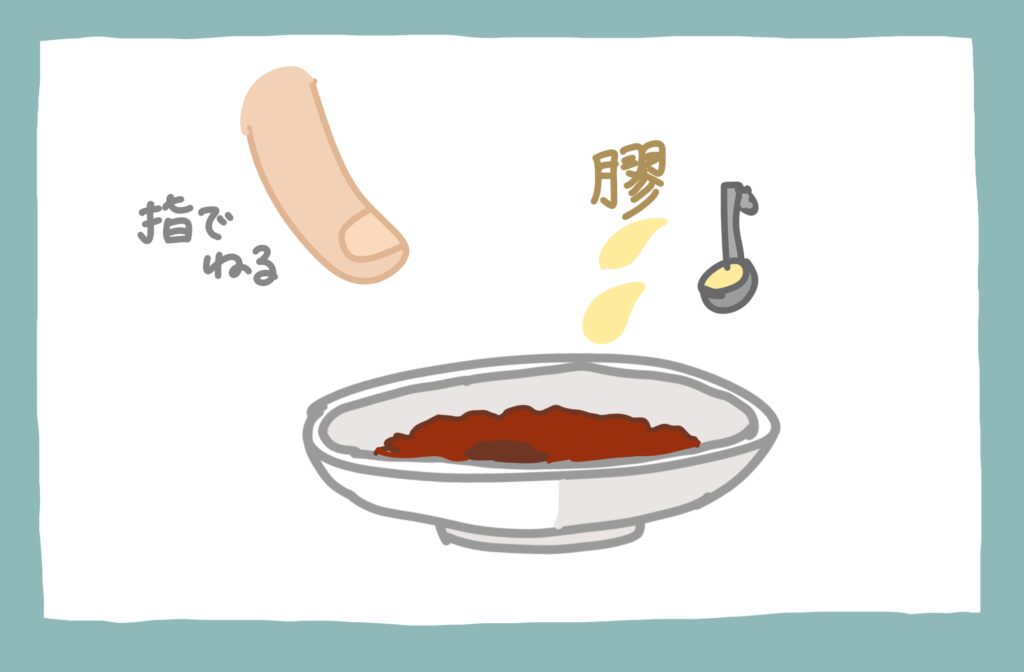
乾燥させれば臙脂の完成!
ゴミやホコリが入らないようラップをします。
膠を混ぜて、水を付けた筆で
水彩のように溶いて使います。
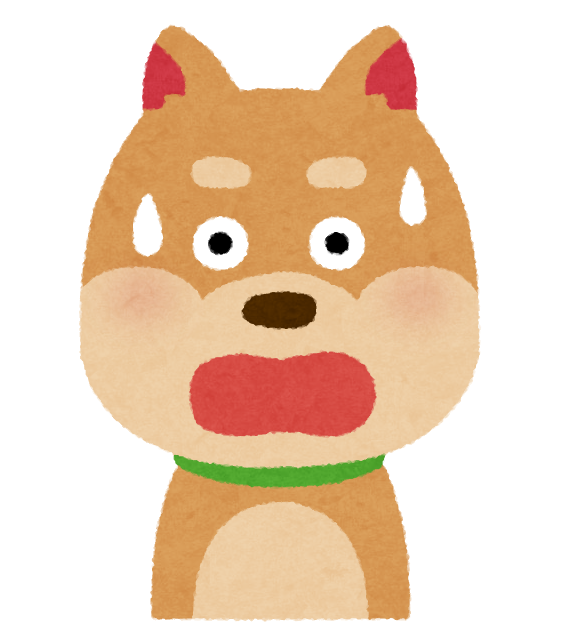
乾燥させて、やっと使えるようになるんだね!
まとめー日本画の臙脂色を解説!ー絵具は昔、綿だった!?
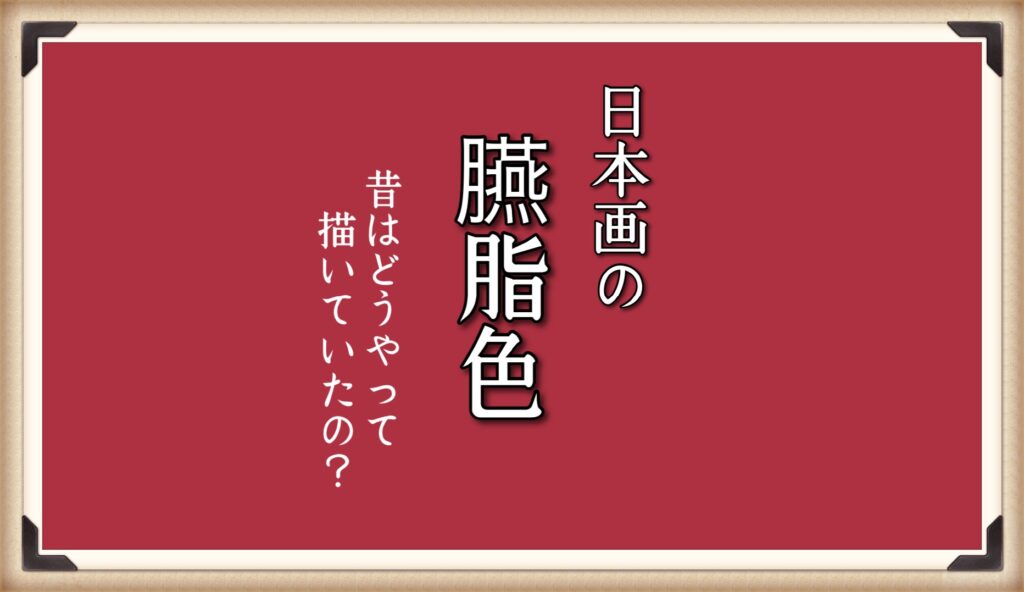
以上、昔使われていた綿の臙脂の使い方でした!
昔は臙脂はチューブでも粉末でもなく、
綿に染み込ませた絵具だったんですね!
普通の日本画絵具のように指で溶かすことが
できません。
綿から紅汁を染み出させ、
乾かして、ようやく使えるようになるのです。
みなさんも、ぜひ昔の絵具に思いを馳せてみては
いかがでしょうか?
丹青指南現代語訳

超充実なのに
古すぎて読みにくいのが難点の
丹青指南を趣味で現代語訳しました。
こちらの原文は
国会図書館デジタルコレクションで
無料でご覧いただけます。
正しい知識や正確な訳が欲しい方は
ぜひ日本画画材と技法の秘伝集を
お買い求めください。
電子書籍&
ペーパーバック発売中!
原文が本で読めるようになりました!
一、臙脂
この絵具は粉絵具ではない。
中国長江沿岸にある江蘇省揚州付近から算出する植物で、
紫草と呼ばれる草から絞って取った紅汁を
(小さいものは円形が12〜15cm、大型のは円形21〜24cmくらいの)
広げた綿に浸して、乾燥させた顔料である。
そして最上品は、北京朝廷の染料に使われているとのこと。
これを絵具として用いるには、
その延ばした綿から絞った紅汁を猪口に移し、
それを湯煎に焼き付けをして使う。
そのやり方が、少々いい加減だと色も良くないので、
少し手数が要るといっても、次に示す焼き付け方をすることで、完全な色相となる。
臙脂の円形が大約21〜24cmのものと仮定して、
その4分の1、もしくは3分の1ほどを切り取る。
それをまた縦横に引き裂いて、碁石大の大きさにして
猪口に入れて、上から熱湯を注ぐ。
(この湯はなるべく少ないのがいい。
でないと焼き付けに時間がかかる)
そのお湯はすぐに紅汁になるので、
猪口の中にある綿を取り出す。
綿に含んでいる紅汁をこの猪口に搾って、
第一番紅汁とする。
その綿をほかの猪口に入れて、
これに熱湯を注ぐと、またその湯も紅汁になる。
そのため、前のようにして綿に含まれている紅汁をしぼり、第二番汁とする。
この二つの猪口には、ホコリやゴミが入らないように仮蓋をして一晩置いておく。
翌朝になって見ると、紅汁はしぼった時よりも、さらによく澄んで鮮やかで明るくなる。
下にある沈殿物は純色のかすなので、紅汁と混ざらないよう、その二つの猪口の紅汁を混ぜて、清潔で汚れていない他の猪口に移す。
そしてこの猪口を、お湯か水を入れた鍋に浸して、それを火にかけて煮沸する。
中の紅汁は徐々に熱されて、猪口の一部にだけ焼き付くので、その猪口を絶えず動き揺らしながら、燕脂の焼き付けを完成させる。
このようにして焼き付けた燕脂の猪口には、
ゴミやホコリが入らないよう紙片を水張りして仮蓋とし、
使うときにはその一端を剥がして、燕脂を使用する。
その後は、元のように蓋紙を張り付けて置いておく。
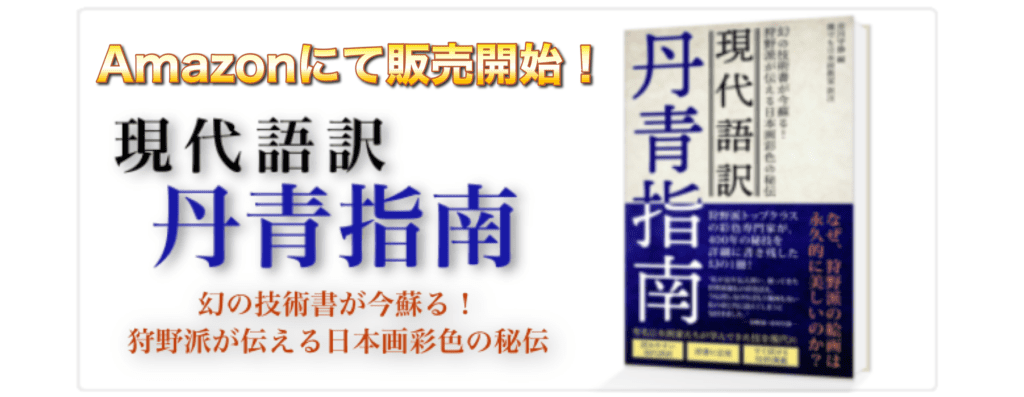


前の記事はこちら!
⇒カーマイン(洋紅)色は原料も意味も虫だった!【日本の伝統色と絵具】
次の記事はこちら!

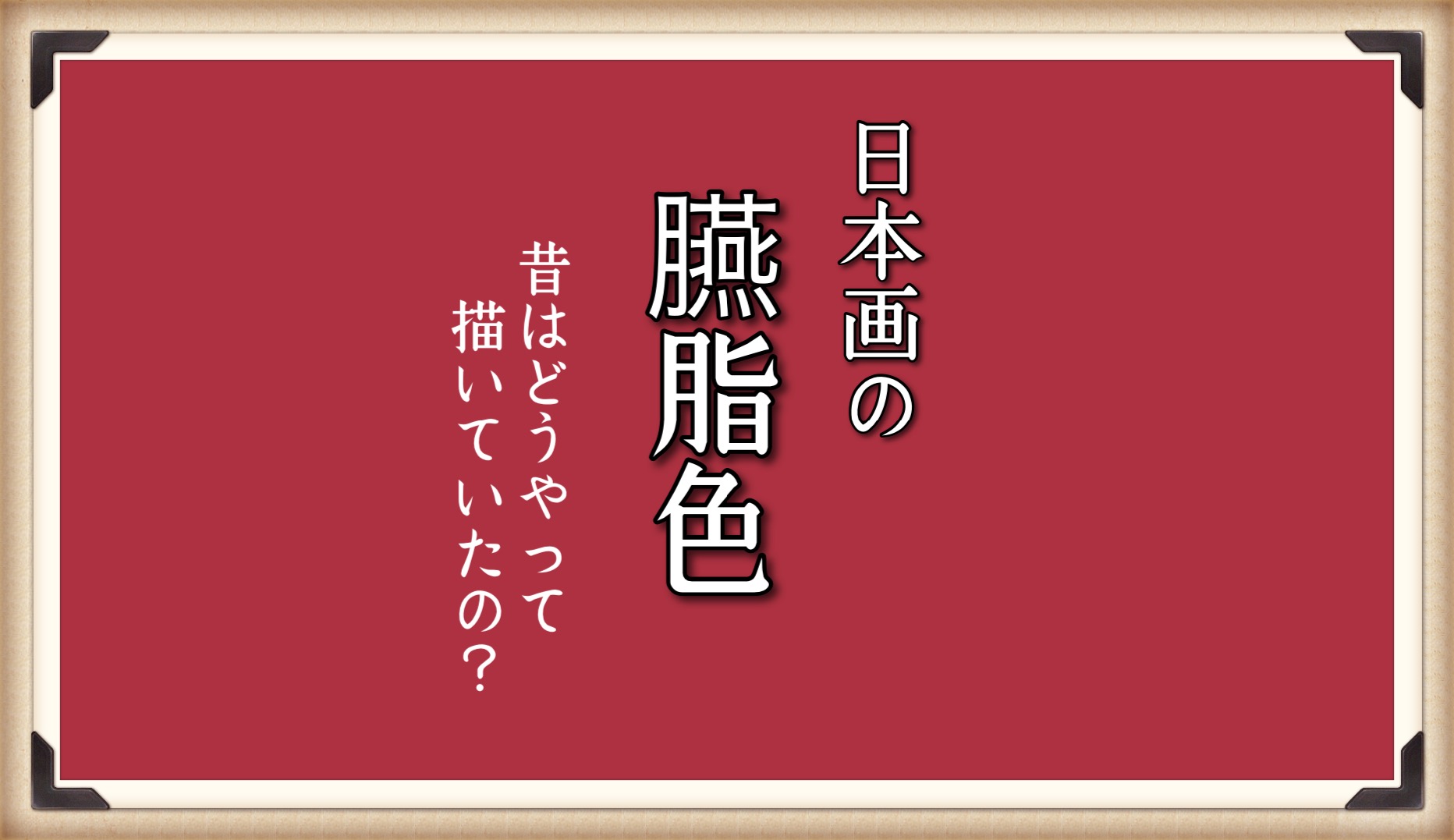
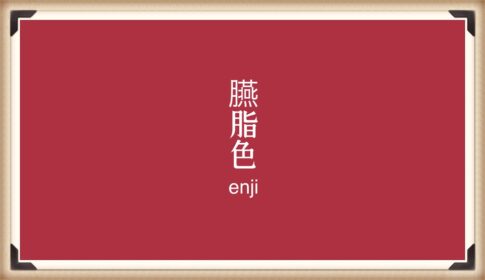



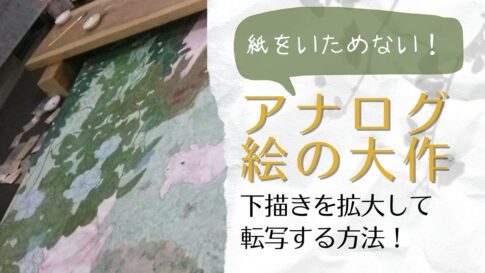
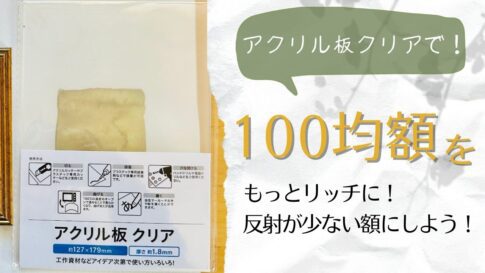
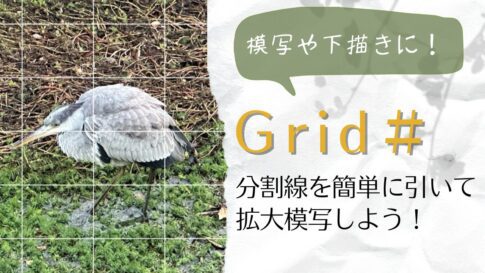










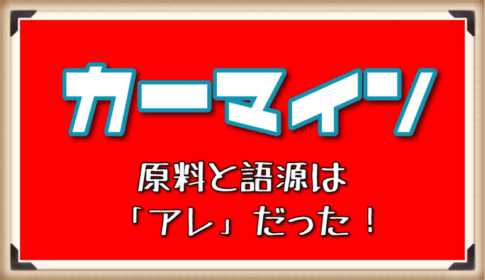
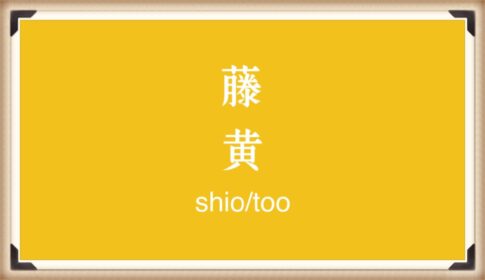

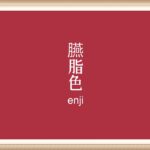


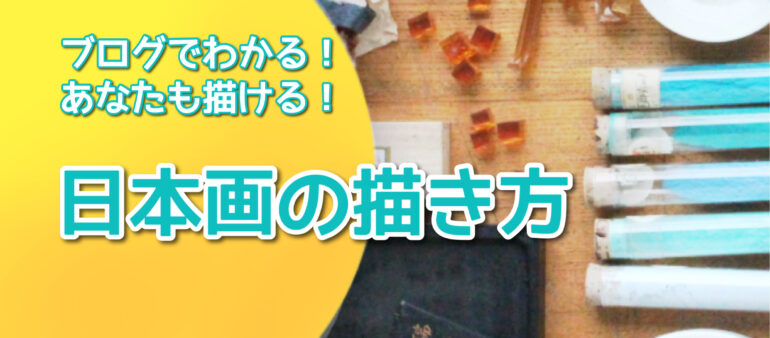
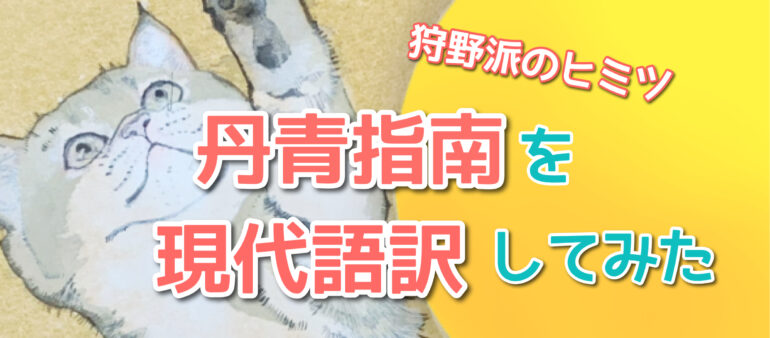
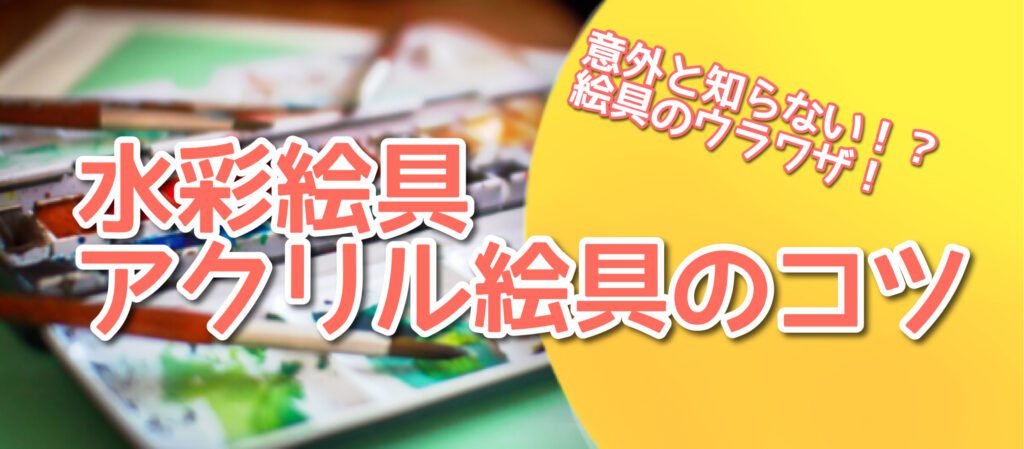
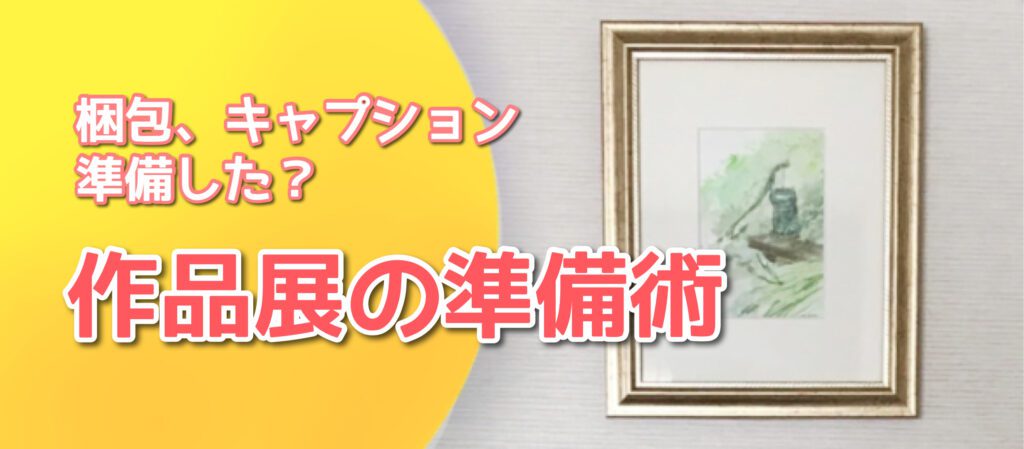
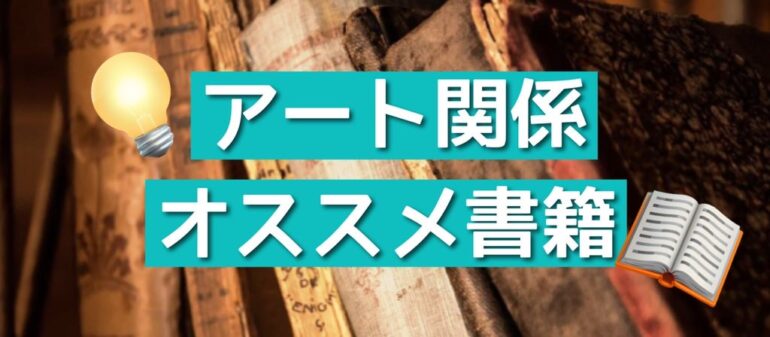
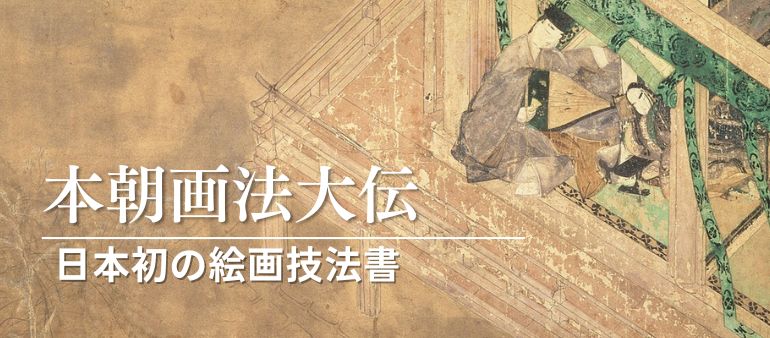
前回の記事で臙脂色が昔から使われていることを知ったよ。
昔はどうやって使っていたの?