こんにちは、日本画家の深町聡美です。
和紙のにじみ止めに使うドーサ液。
その作り方は、
膠液にミョウバンを入れるというシンプルなもの。
しかし一体どうして化学薬品も入っていない
膠とミョウバンだけで、
にじみ止め効果が生まれるのでしょうか?!
この記事では
ミョウバンの作用を科学的に解説し、
ドーサ液の仕組みを解説いたします!
ドーサの関連記事はこちら!
➡【初心者向け】日本画のドーサ液の引き方、作り方をイラスト付きで解説!
➡【日本画】狩野派のドーサ液の作り方とは?効果はあるの?【丹青指南現代語訳】
Contents
ドーサ液の効果とは?―ドーサ液にミョウバンを入れる理由

……最初に結論だけ書くと、
ドーサにミョウバンを入れる理由は
「料理」
特に煮崩れ防止と同じ理由です!
膠のタンパク質をミョウバンが固めるためなのです。
ドーサ液を塗らないといけない、その理由
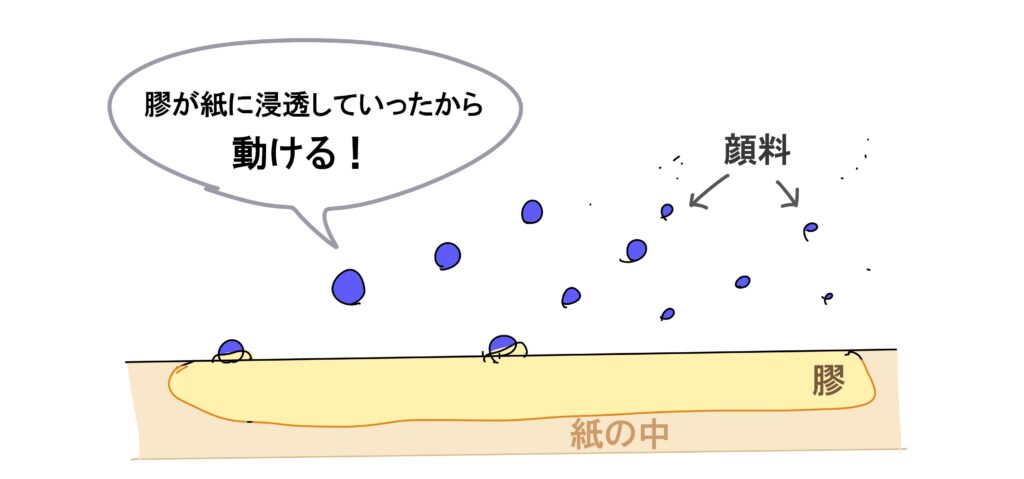
和紙や絵絹は吸水性がありますよね。
水を垂らすと、紙の中に吸い込まれて行き
水を弾くことはありません。
なので、そのまま絵具を塗ると、
膠液のみが紙に浸透して、
顔料(色の素になる成分)は定着しません。
つまり、触っただけで絵具が取れてしまったり
少し重ね塗りをしただけで、
下の絵具が動いてしまったりと、
作業を進めにくくなってしまうのです。
なぜドーサ液は水を弾くの?

ところがドーサ液を塗ると、
紙の表面に薄い被膜が作られます。
こうすることで、紙の吸水性を抑え、
膠水の浸透を防いでいるのですね!
これで紙の表面には膠水が残り、
(=水を弾き)
顔料がしっかりと定着する。
つまり、剥がれにくく、
発色が良くなりやすいのです!
ここまでで、ドーサ液の効果がなんとなく
分かったのではないでしょうか?
鍵になるのは、
紙の表面の「被膜」ですね。
(ガラス質の被膜とされる)
ミョウバンには膠と混じることで
この「被膜」を作る作用があるのです!
なぜドーサ液作りでミョウバンを入れるのか?
ドーサ液中のミョウバンはタンパク質を固める!

ミョウバンには特徴的な作用があります。
ミョウバンを製造している
大明化学工業株式会社の説明を見てみましょう!
【カリミョウバンの性質について】
アンモニウムミョウバン/大明化学工業株式会社
水溶液は加水分解により酸性(1%液PH=3.5)を呈し、収れん性がありタンパク質を凝固させる。
このように、
ミョウバンはタンパク質を凝固させる作用
があります!
細胞膜と結合して固めてしまうのだそうです。

また、タンパク質は固まる事で
「水不溶化」
つまり水に溶けなくなる、乾いたら耐水性になるのです!
この作用は、きちんと論文で証明されています。
ミョウバン中の硫酸アルミニウムカリウム(PAS)やグルコノ-δ-ラクトン(GDL)がパンケーキなど膨張剤として使用されているが,(中略)
ミョウバンとその代替化合物の添加がパンケーキの膨張と構成タンパク質に与える影響
PASやGDLの添加量を増やすと,パンケーキ中の水溶性タンパク質(アルブミン区分)の比率が減少し,代わって水不溶性の区分,特に70 %エタノール可溶性タンパク質(グリアジン区分)や酸可溶性タンパク質(可溶性グルテニン)および不溶性グルテニン区分が増加する傾向にあり,全体的にタンパク質の水不溶性が増加する傾向があった.
齊藤 紅, 簑島 良一, 椎葉 究

ドーサ液に使われるミョウバンには
- ミョウバンはタンパク質を凝固させる
- 凝固したタンパク質は、耐水性になる
作用があることが分かりました。
ここで出てくる「タンパク質」こそが
「膠」なのです!
ミョウバンは膠のタンパク質を固めて、
紙の上に耐水性の被膜を作っているという訳です!
この、タンパク質を固める作用は
料理の際に、野菜の煮崩れ防止にも
使われているそうです。
知らないともったいない みょうばんの驚くべき活用術/ニチノウ食品
ドーサ液中の膠の主成分はタンパク質!

「膠はタンパク質」
と言ってもピンと来ないかもしれません。
ですが、膠の主な原材料は
動物の皮や骨、腸や腱です。
これを煮出してコラーゲンを抽出し、
固めて乾かした物が膠。
そうです、膠はタンパク質の塊なのです!
だから、ミョウバンは膠を固めて
耐水性の膜を作ることができるのです!
【追記:2022/04/19】
膠テンペラのようにミョウバンをドーサに
混ぜても良いのか?中間ドーサは不要になるか?
というご質問を頂きましたので
回答をこちらにも添付いたします。
?ミョウバンと膠を混ぜた物で岩絵具は接着可能か?
▶︎やったことがないので正確な所は
分かりかねますが、凝固する前に使えば
接着は可能だと思います。
ミョウバンの比率にもよるでしょう。
?なぜ日本画ではしないのか?
▶︎ 酸性が強過ぎるから(保存性が下がる)
紙の経年による損傷は、phが原因の一つとされています。
ミョウバンは酸性なので、多用する事で
紙の劣化を早める可能性があると推測します。
日本画では和紙へのドーサ引きの後には、
アルカリ性の胡粉を引いて中和します。
▶︎膠の柔軟性が無くなるから(剥がれる)
以前中間ドーサにミョウバンを入れ過ぎた時、
作品の表面に結晶ができ、
絵具を弾いて乗せられない、
表面が固くなることがありました。
この事から、膠の柔軟性が失われていると
感じました。
日本画において柔軟性が失われるという事は、
紙の弛みに表面の岩絵具層が付いていかない。
つまりひび割れのリスクが高くなる
のではないかと考えます。
アルカリ性の炭酸カルシウムなどを下地にした
膠テンペラ。
この場合、基底材(紙、キャンバス、板)の
収縮が和紙よりも少なく、
日本画に比べて顔料の粒も小さく、
酸による劣化も無いため、
膠とミョウバンを混ぜて描いても
問題がないのだと思われます。
まとめ―ドーサ液にミョウバンを入れる理由
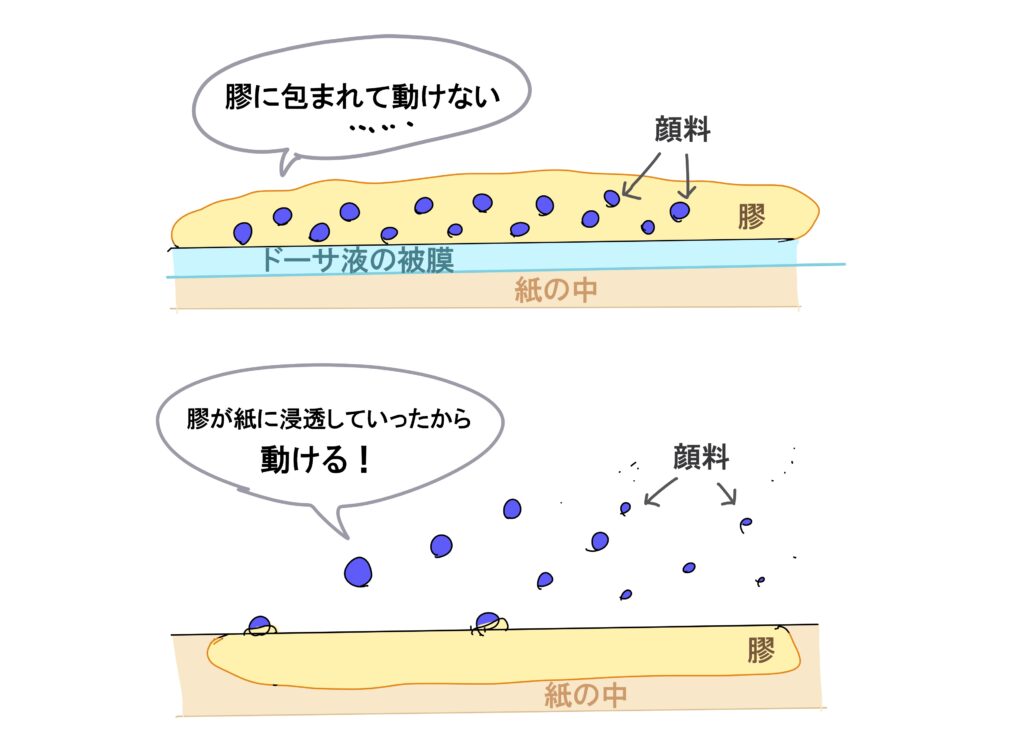
ミョウバンには
- 膠(タンパク質)を凝固させる作用
- 膠(タンパク質)を水不溶性にする作用
がありました。
この効果によって、
紙の表面に耐水性の被膜が作られます。
だから紙の上に墨で描いても滲まないし、
顔料がしっかり接着することができるのです。
これこそが、ドーサ液の仕組みという訳ですね!
普段なんとなく使っているドーサ液。
ですが、先人の知恵が詰まったにじみ止め
だったのです。
ドーサ液は色々な基底材に使えるので、
ぜひ一度作ってみて下さい!
ちょっとしたロマンを感じる事が
できるかもしれませんよ。
ドーサ液の作り方・塗り方は関連記事で!
前の記事はこちら!
➡【初心者向け】日本画のドーサ液の引き方、作り方をイラスト付きで解説!
次の記事はこちら!
➡誰でもリアルに描ける!?絵やイラストを写実的に描くための練習法

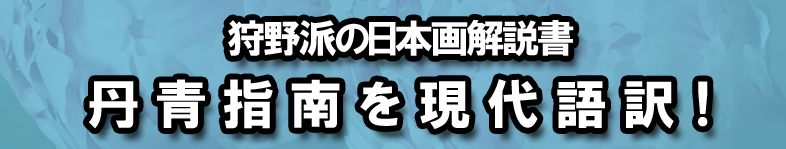

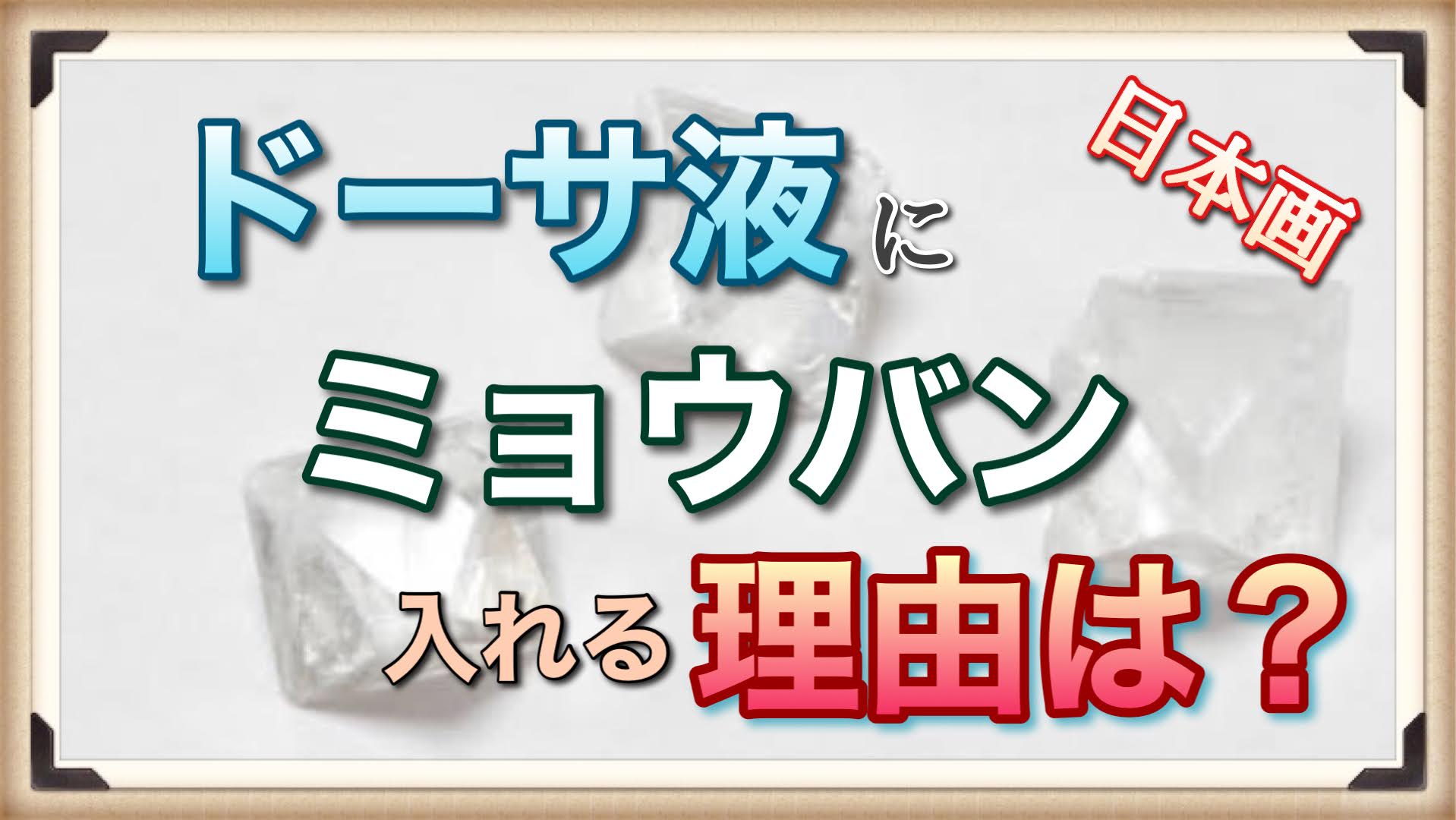

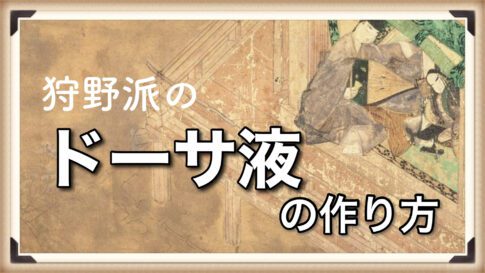













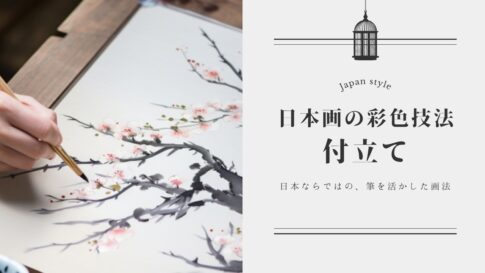

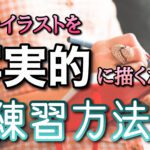



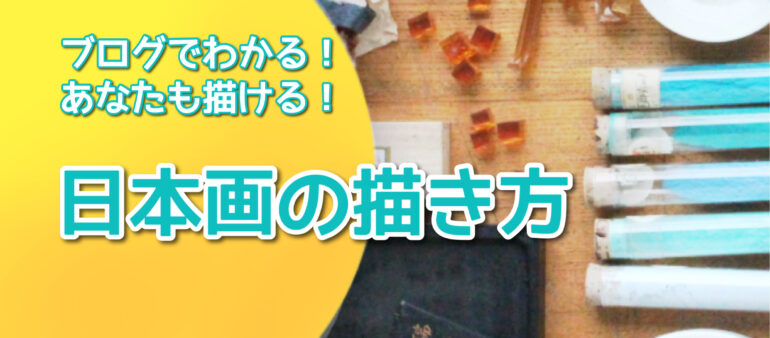
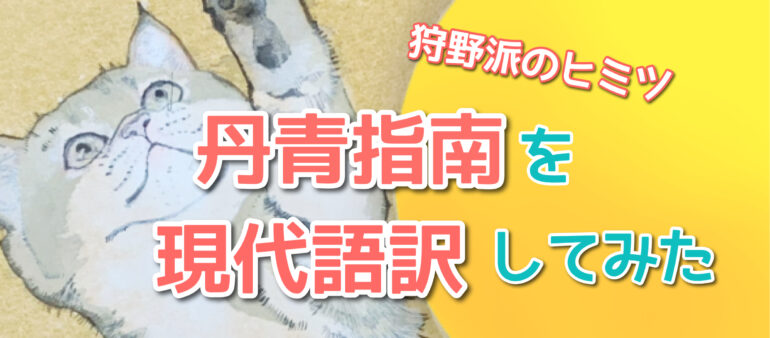
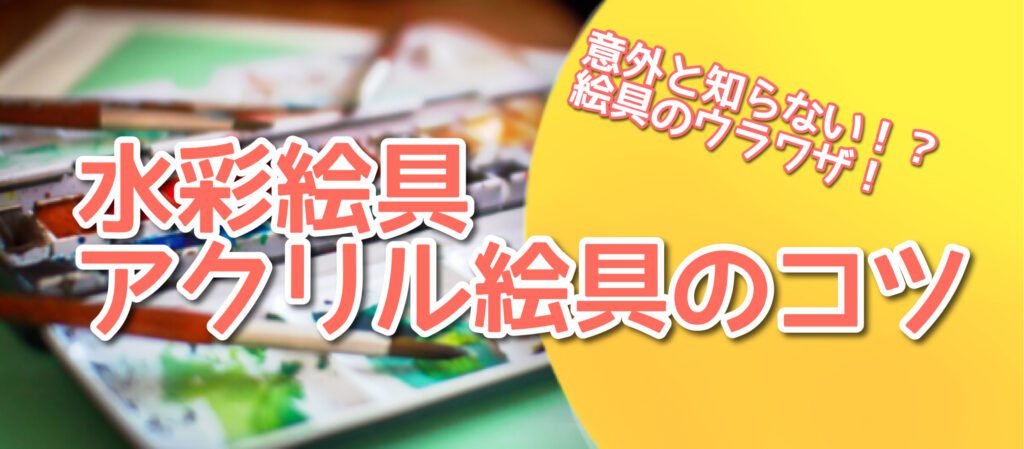
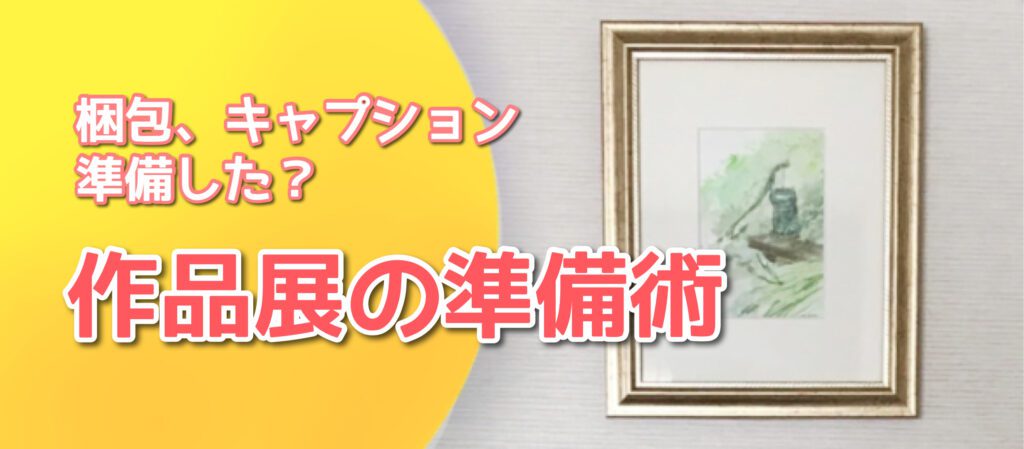
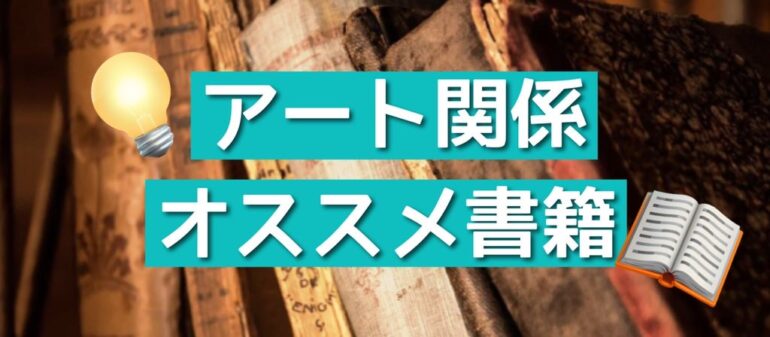
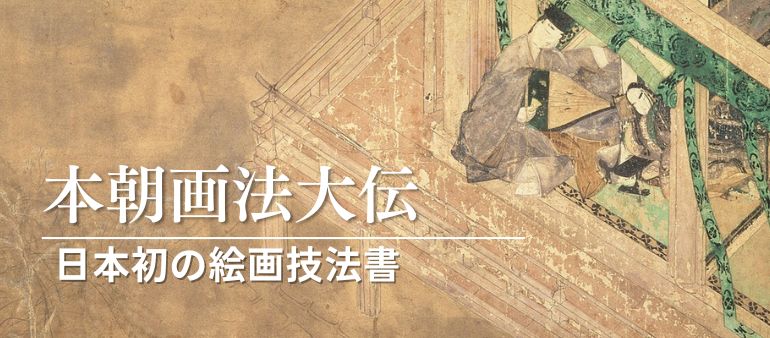
なんで膠にミョウバンを混ぜるだけで滲み止めになるの?